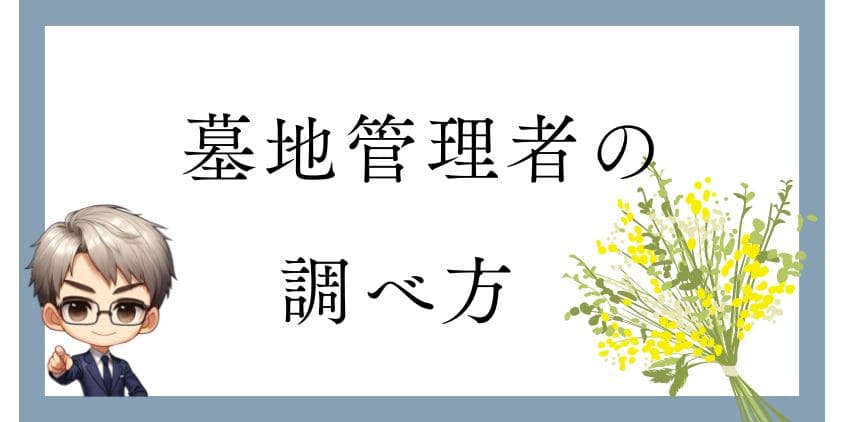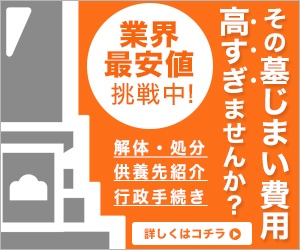「墓地管理者がわからない!」
「墓地管理者の調べ方は?」
「墓地管理者はどこにいるの?」
墓地管理者が必要だと言われても、どこを調べればいいのかわかりませんよね。
この記事では、墓じまいや改葬に必要な墓地管理者の調べ方を紹介します。
墓地管理者とは、お寺とか霊園、自治体などのお墓を管理してる団体の中の個人で、資格や届け出はないです。
ただ、共同墓地や集落墓地、みなし墓地の場合、墓地管理者がいない場合が多く、墓地管理組合や村で管理してるときもあるので、調べるのが大変です。
基本的には、役所の墓地台帳の閲覧がおすすめです
いろいろな場合がありますので、詳しい探し方を解説していきます。
参考:墓じまいの流れと費用
- 墓地管理者の調べ方
- 墓地管理者の役割と必要性について
- 墓地の種類ごとの管理者について
- 管理者が不明な場合の対策方法
墓地管理者の調べ方を詳しく解説
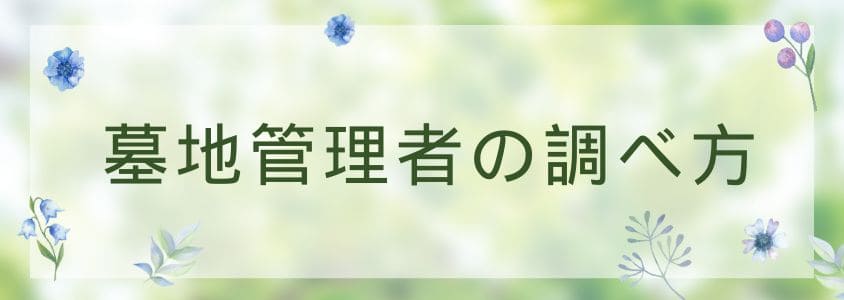
墓地管理者とは?
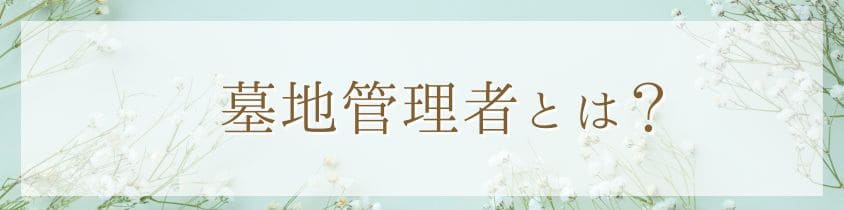
墓地管理者は、墓地の維持・管理を行う重要な存在です。
墓地管理者の役割は、墓地の清掃や修繕、利用者からの問い合わせ対応、法的な書類の管理など。
墓じまいには墓地管理者が必ず必要です。
墓地の種類によって、墓地管理者が違います。
| 種類 | 所有者 | 墓地管理者 |
|---|---|---|
| お寺 | 宗教法人 | 住職 |
| 民間墓地 | 公益法人 | 管理会社 |
| 公営墓地 | 自治体 | 職員 |
| 個人墓地 | 個人 | 個人 |
| 共同墓地 | 町内会や個人 | 町内会長など |
所有者は墓地がある土地の所有者で、所有者の依頼で墓地管理者が管理・整備をしています。
お寺
お寺の中にある墓地(土地)は、お寺という宗教法人の所有になります。
墓地管理者は人でなくてはならないので、そのお寺(宗教法人)の住職になります。
つまり、次のような仕組みになっています。
- 墓地(土地)はお寺(宗教法人)の土地
- 使用者は永代使用料をお寺に払う
- 使用者は石材店から墓石を買って立てる
- 住職がお墓を管理・維持する
お寺の中には管理会社に依頼してるお寺もあります
民間墓地・霊園
民間霊園は、公益法人が運営する墓地です。
公益法人とは、公益の増進を図るのを目的とした民間の法人です。一般社団法人とNPO法人の中間に位置します。
墓地(土地)は公益法人が所有し、管理者は職員です。
公営墓地
公営墓地は、地方自治体が運営する墓地です。
市営墓地や町営墓地のことで、永代使用料と年間管理料が非常に安いのが特徴です。
墓地(土地)は自治体(市や町)の持ち物で、管理者は役場の職員です。
個人墓地
個人墓地は、個人が所有している土地に立っている墓地です。一族が代々利用しています。
墓埋法(昭和23年施行)以前からある墓地で、都道府県知事の許可がない墓地は無許可墓地、許可を受けた墓地をみなし墓地と呼びます。
みなし墓地は、役場にある墓地台帳に、所有者と管理者が登録されています。
無許可墓地の場合は、役場と相談して登録するようにします。
共同墓地
共同墓地は、複数の家族や地域住民が共同で利用されてる墓地です。
こちらも墓埋法(昭和23年施行)以前からある墓地が多く、みなし墓地として登録されていれば、役場の墓地台帳に記載があります。
登録されてない場合(無許可の場合)は、役場に相談すると、墓地組合を立ち上げるように指示されます。
墓地組合の管理者は町会長とか今まで管理してきた方になってもらうケースが多いです。

次に、墓地管理者の調べ方を詳しく解説します。
墓地管理者がわからない時の7つの調べ方
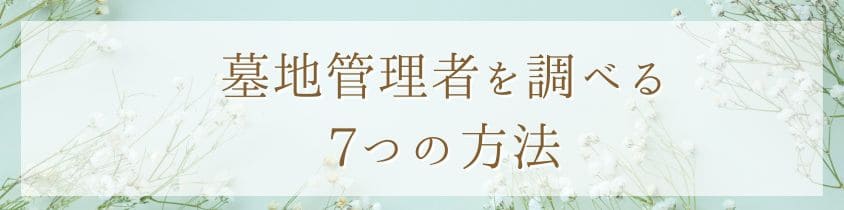
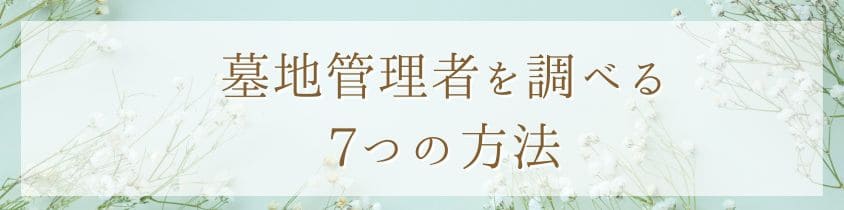
お墓がお寺や管理霊園にあれば、住職や管理会社に問い合わせるとすぐに分かります。
個人墓地や共同墓地、よくわからない墓地の墓地管理者を調べるには、7つの方法があります。
- 自治体に問い合わせる
- 親族や知人に問い合わせる
- 地区の古老に問い合わせる
- 石材店に問い合わせる
- 葬儀社に問い合わせる
- お寺に問い合わせる
- 登記簿謄本を調べる
1. 自治体に問い合わせる
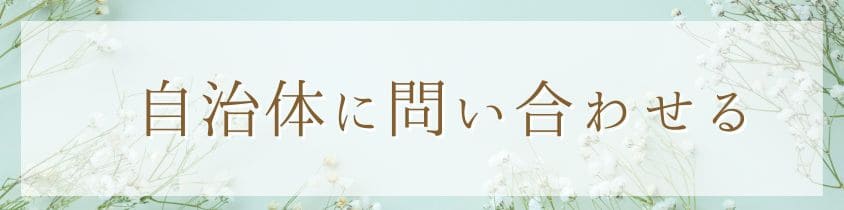
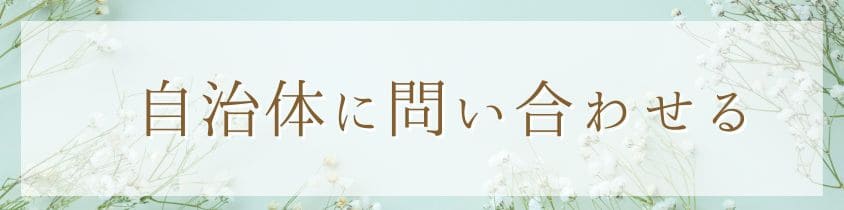
よくわからない墓地の管理者を調べる最初のステップは、自治体への問い合わせです。
自治体には墓地管理者の届け出が義務付けられており、記録(墓地台帳)があります。
自治体の墓地台帳を見れば、正確な情報を得られ、手続きもスムーズに進められます。
2. 地元の親族や知人に問い合わせる
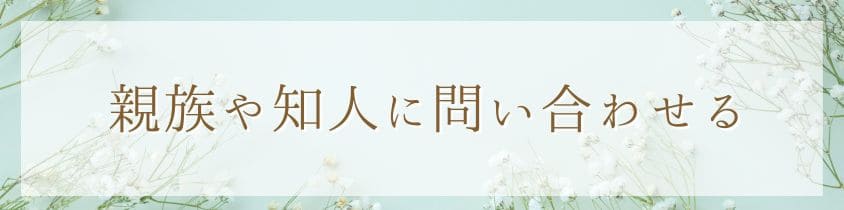
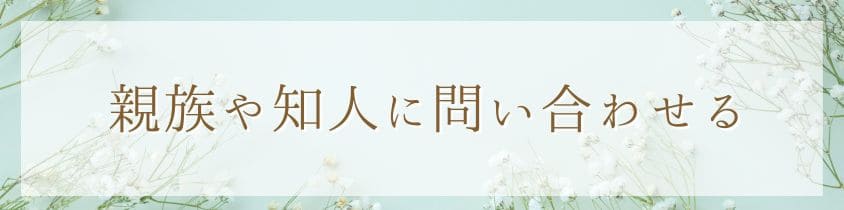
墓地の管理者を知っている可能性が高いのは、親族、知人です。
たとえお墓参りには来ていなくとも、親戚の誰が立てたのか、誰が守ってきたのか、管理してきたのか、知ってる方も意外にいらっしゃいます。
墓じまいの連絡のついでに、誰に相談すれば良いのか、誰が祭祀承継者なのかを聞いてみるのをおすすめします。
3. 町内会長や自治会長に問い合わせる
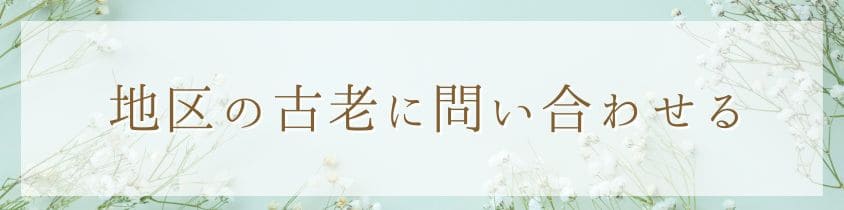
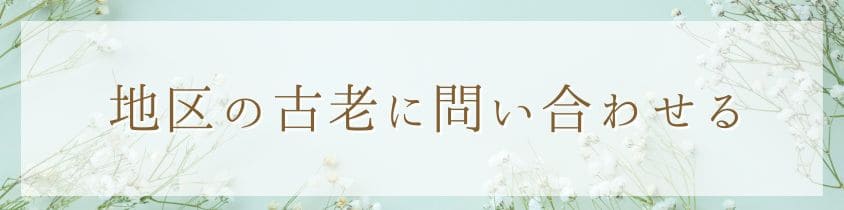
地域の町内会長や自治会長も、墓地の管理者についての情報を持っているのが多いです。
共同墓地にあるお墓の数だけ関係者がいるので、こういった問合せも数多く受けてるはずだからです。
地域のまとめ役の方たちは地域の様々な問題に対応しており、墓地管理者の情報も管理しています。
現町内会長だけでなく、経験者の方たちにもお話をお伺いしてみましょう。
4. 石材店に問い合わせる
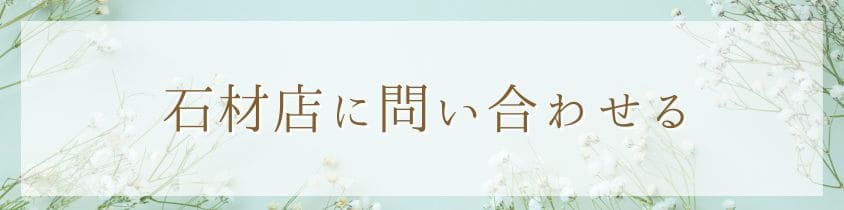
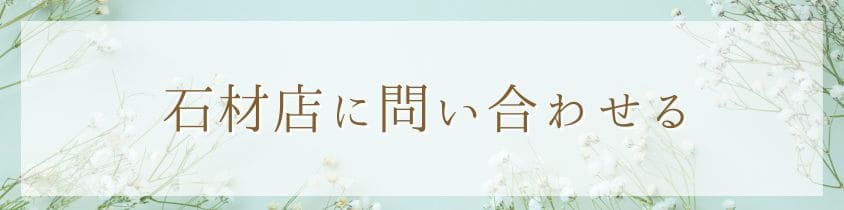
いつの時代でも、墓地は石材店が立てます。
墓地を立てたり売った石材店には、その墓地に関する記録が残ってるはずです。
地域の石材店を何件も回って、その墓地の記録がないか探してみるのもひとつの手です。
5. 葬儀社に問い合わせる
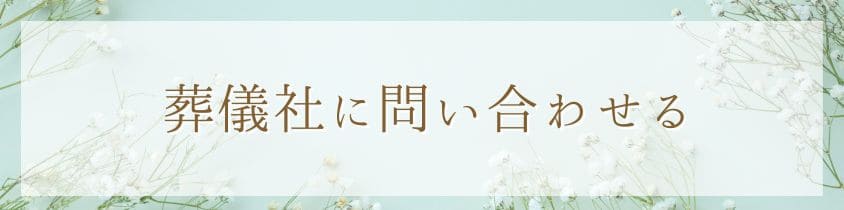
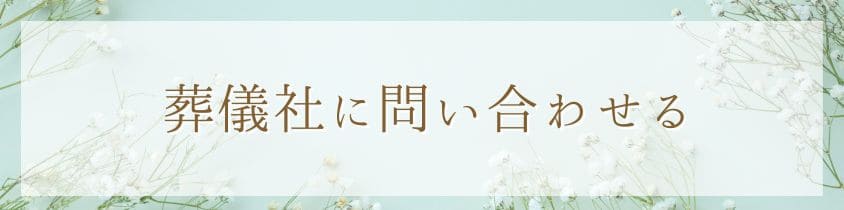
葬儀社も墓地についての情報を持っているケースがあります。
法事やお葬式などで、お墓の所有者と関わるのが多いからです。
葬儀社への問い合わせで、管理者の情報を得られる可能性があります。
6. お寺に問い合わせる
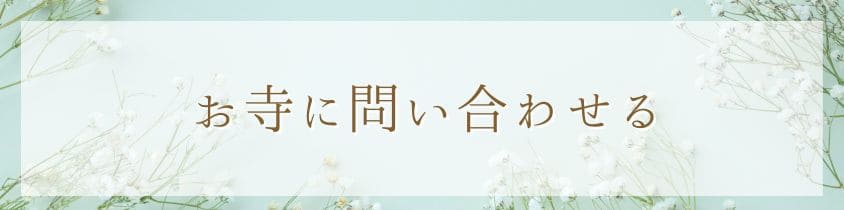
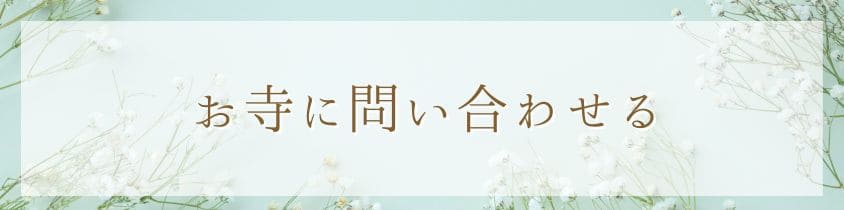
特に古い墓地の場合、お寺が管理しているときがあります。
実際の管理者が誰なのか、お寺に問い合わせをすれば判明する可能性があります。
お墓は閉眼供養や魂入れをする必要があるので、記録が残ってるかもしれません。
7. 登記簿謄本を調べる
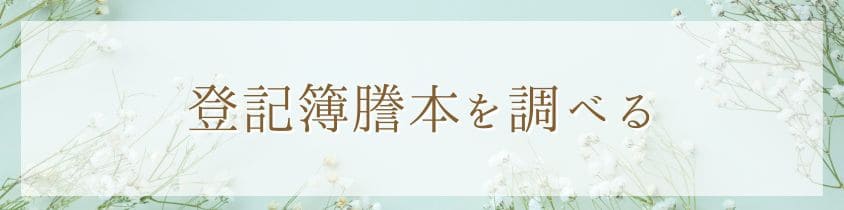
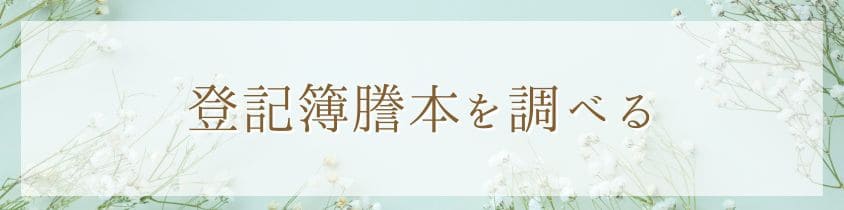
最終的に、登記簿謄本を確認するのが有効です。
土地にはかならず所有者がいて、登記簿謄本には土地の所有者情報が記載されています。
個人墓地なら、墓地(土地)の所有者が管理者になります。
共同墓地なら、墓地(土地)の所有者に墓地管理組合を作ってもらいましょう。
どうしてもわからないときの対策
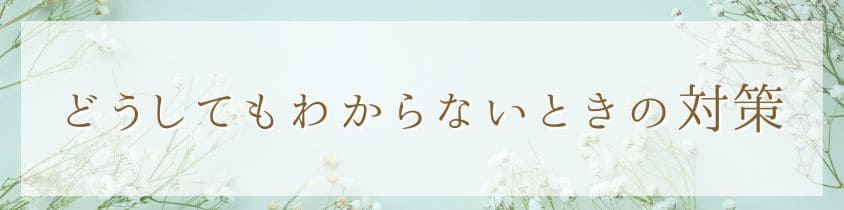
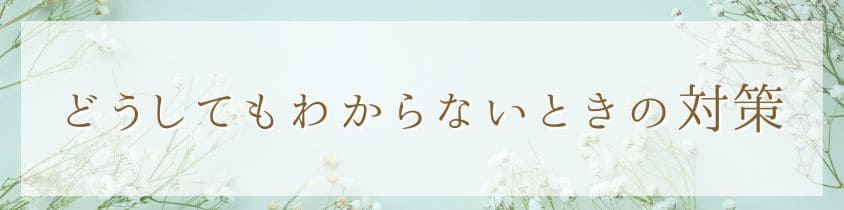
墓地管理者がどうしてもわからない場合、一般的に次の3つの対策が考えられます。
- お墓(土地)の所有権の登記
- お墓の管理者を決める
- 墓地管理組合を作ってもらう
お墓(土地)の所有権の登記
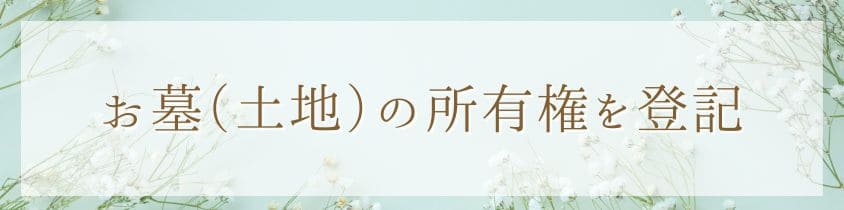
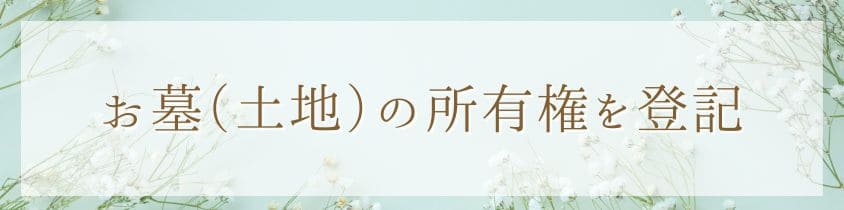
登記簿謄本に墓地として登録してない場合とか、すでに亡くなってる人の場合です。
その場合は役場や法務局などと相談してから、祭祀財産もしくは相続財産として所有権の登記を行います。
その後に管理者も決めてから、役場の墓地台帳に登録しましょう。
墓地管理者を決めて届出する
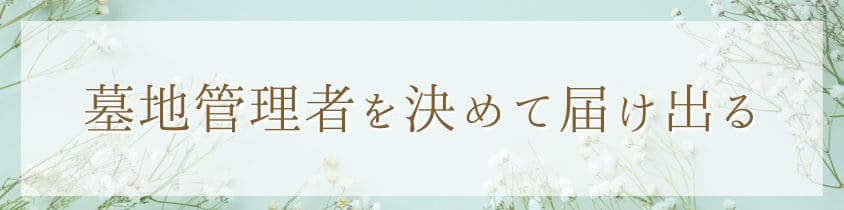
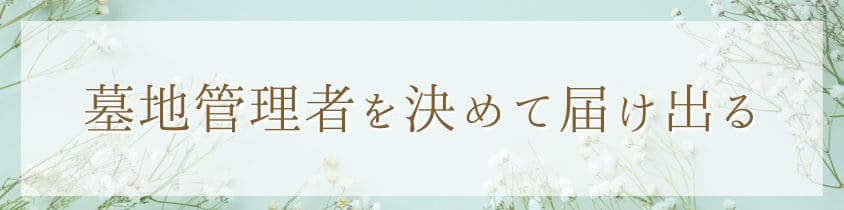
墓地台帳に管理者が載っていない場合とか、亡くなってるときもあります。
その場合、新たに管理者を決めて、自治体に届け出る必要があります。
土地の登記簿謄本に載ってる所有者が管理者になります。
墓地管理組合を作ってもらう
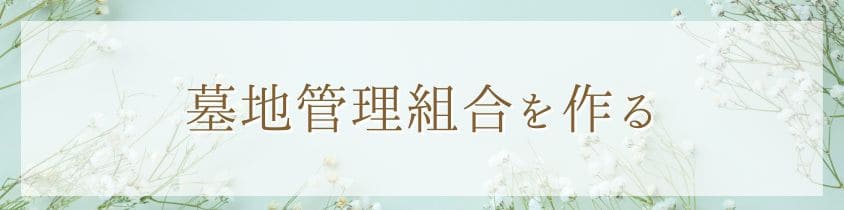
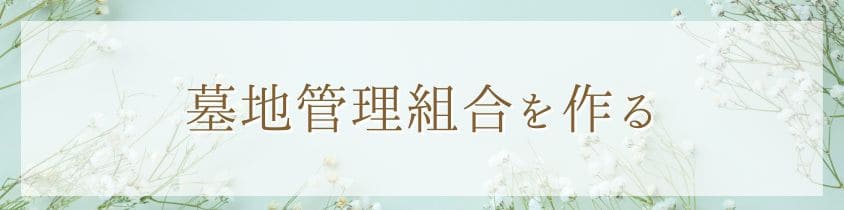
共同墓地なのに墓地台帳に載ってなかったときには、町会長や自治会長に墓地管理組合をつくってもらいましょう。
墓地管理組合は、墓地の管理運営を共同で行うための組織です。
管理者は町会長や自治会長にやってもらいます。



いずれにせよ、役場と相談ですね
墓地管理者の調べ方に関するその他の情報
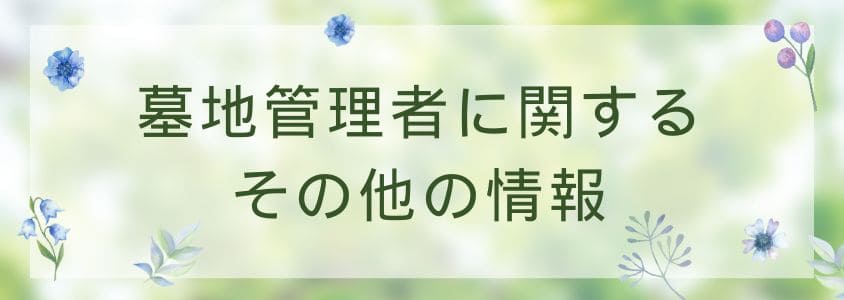
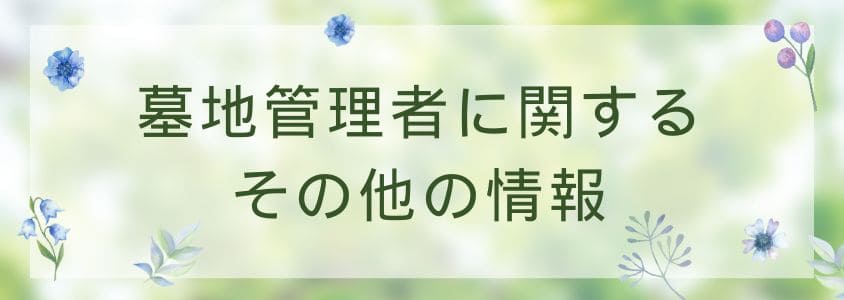
墓地管理者の責任と義務
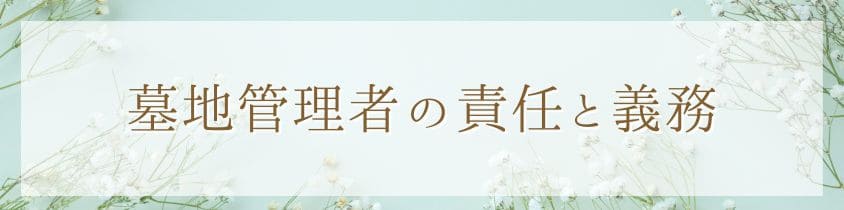
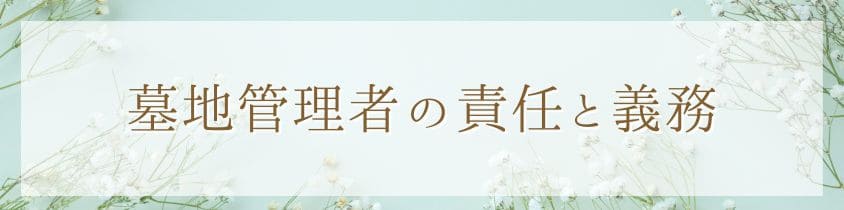
墓地管理者は次のような責任と義務があります。(参考:墓埋法)
- 図面や帳簿の管理
- 自治体への報告
- 墓地全体の維持管理・保全
図面や帳簿の管理
墓地管理者は、図面や帳簿の管理が義務付けられています。
- 墓地使用者等の住所及び氏名
- 埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
- 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
- 墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類(引用:墓地埋葬法規則7条)
これらの図面や帳簿は、開示要請があれば開示しなくてはならないと規定されています。
墓じまいの際には、これらの帳簿を閲覧して、中に誰が、何柱入っているのかなどを確認しましょう。
自治体への報告
墓地管理者は、自治体への報告も行います。
毎月の埋葬や火葬の状況を5日までに報告する義務があります。
自治体への報告が行われて、墓地の状況が正確に把握され、適切な管理が可能となります。
墓地全体の維持管理・保全
墓地管理者は、墓地の共用部分の環境整備や掃除も行います。
これにより、利用者が快適に訪問できる環境が維持されます。
例えば、ある霊園では、管理者が定期的に共用部分の清掃を行い、利用者から高評価を得ています。
利用者に快適に墓地を訪れてもらえるように、共用部分の整備が管理者によって行われています。
墓じまいの書類とは?
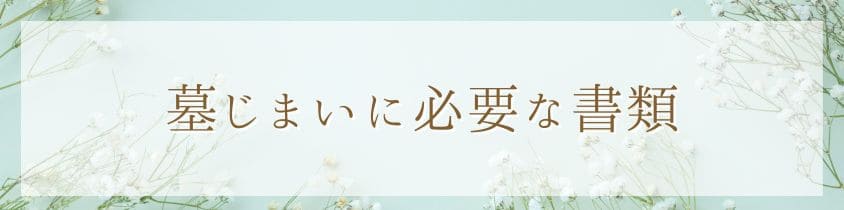
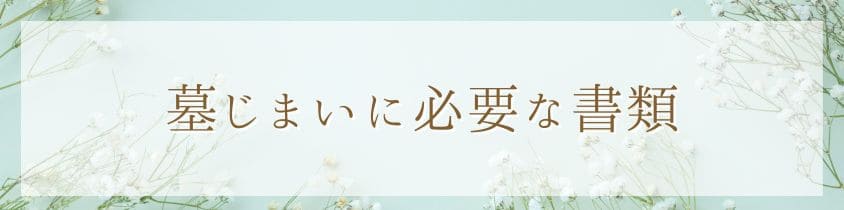
墓じまいを行う際には、改葬許可証が必要です。
改葬許可証を得るためには、基本的に3つの書類が必要です。
- 改葬許可申請書
- 埋葬許可証
- 受入証明書
改葬許可申請書
改葬許可申請書は、お墓がある自治体のHPでダウンロードできます。
改葬許可申請書に記載する内容の一例は次のとおりです。
- 遺骨の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
- 埋葬されてる場所
- 埋葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者の住所、氏名、続柄、墓地使用者との関係、連絡先
埋葬許可証
埋葬許可証は、自治体によってもらい方が違います。
一般的には次の2通りがあります。
- 現在の墓地管理者にもらう
- 改葬許可申請書にサイン、押印してもらう
自治体によって違いますので、確認してください。
受入証明書
受入証明書は、新しい供養先から交付してもらいます。
新しい供養先の墓地管理者がいない散骨や自宅供養の場合、改葬許可申請書の改葬先を、「散骨」とか「自宅」と記入すれば大丈夫です。
改葬許可証
上記の改葬許可申請書と受入証明書、埋葬許可証を、お墓がある自治体の窓口に提出します。
2週間くらいで、改葬許可証が発行されます。
改葬許可証が発行されれば、墓じまいできます。
おすすめの代行業者3選
青森県で墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。
「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から


「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。
サービス内容はこちら。
- お墓の撤去
- 離檀代行・サポート
- 行政手続きサポート
- 撤去業者持ち込み交渉
- 墓じまい全体のサポート
離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。
サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。
公式サイトで無料相談してみてください。
安心・安全の「イオンの墓じまい」


日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。
基本的なサービスがワンセットになっています。
- 行政手続き
- お骨の取り出し
- 墓石の解体・処分
- 墓地を更地に戻す
- お骨の受け渡し
公式サイトから詳細の金額をご確認ください。
\ 無料相談はこちら /



イオンカードも使えます
すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」


面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。
サービス内容はこちら。
- 行政手続き代行
- ご遺骨の取り出し
- 墓石の解体・処分
- 墓所の変換
行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。
公式サイトから詳細をご確認ください。
参考:代行業者の選び方
まとめ:墓地管理者の調べ方
この記事のまとめです。
- 墓地管理者がわからない場合、自治体に聞く
- 墓地管理者名は自治体の墓地台帳に
- 墓じまいには墓地管理者のサインや押印が必要
- 墓地管理者を調べるには7つの方法がある
- 地元の親族や知人に聞く
- 地区の古老に聞く
- 石材店に聞く
- 葬儀社に聞く
- お寺や霊園に聞く
- 登記簿謄本を調べて土地の所有者に聞く
- 共同墓地の場合、町内会長や自治会長に
- 墓地の種類により管理者が異なる
- お寺は住職が管理者であることが多い
- 民間霊園は公益法人の職員が管理者
- 公営墓地は自治体の職員が管理者
- 個人墓地は土地の所有者が管理者
- どうしても管理者がわからない場合は、役場と相談
- 墓地管理者が必要な手続きは埋葬許可証の発行
- 墓地管理者は墓地の清掃や修繕も行う
- 墓地管理者の確認は地域の歴史や古い記録が参考に



最後まで読んでいただきありがとうございました!
厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要