お墓の承継者がいない、あるいは遠方に住んでいて管理が難しいといった理由から、墓じまいを検討する方が増えています。
特に、先祖代々受け継いできた墓石をどう扱うべきか、悩む方は少なくありません。
田舎にあるお墓の放置は避けたいものの、墓じまいをするにしてもお墓の墓石を撤去する費用が気になりますし、そもそも墓じまいにお金がないと一歩を踏み出せないケースもあるでしょう。
一方で、必ずしも墓じまいが唯一の選択肢ではありません。
墓じまいをしなくても大丈夫な場合や、墓じまいをしないで永代供養を選ぶという方法も存在します。
この記事では、墓じまいをする際に墓石をそのままにしたいとお考えの方へ、様々な選択肢を詳しく解説します。
墓石の処分方法、墓石処分を自分で行うことの可否、そして、いらなくなった墓石はどうなるのかという基本的な疑問から、墓じまい後の墓石再利用や墓石リメイクの可能性を紹介します。
さらには利用が期待される墓じまい補助金の情報まで、あなたの悩みに寄り添い、後悔のない選択をするための一助となる情報をお届けします。
- 墓じまいで墓石をそのままにするメリット・デメリット
- 墓石の処分方法と自分で行うことの可否
- 墓石の再利用やリメイクといった新しい選択肢
- 墓じまいにかかる費用と利用できる補助金の有無
墓じまい 墓石そのまま放置するリスクと対処法

- 田舎の墓を放置するとどうなる?
- 墓じまいをしなくても大丈夫なケースとは
- 墓じまいしない永代供養という選択肢
- 墓石の処分方法
- 墓石処分は自分でできるのか
- いらなくなった墓石はどうなるのか
田舎の墓を放置するとどうなる?
田舎にあるお墓の管理が難しくなり、そのまま放置してしまうと、最終的に「無縁仏」として扱われ、撤去されてしまう可能性があります。
お墓の管理費が長期間にわたって支払われず、承継者とも連絡が取れない状態が続くと、墓地の管理者は法律に基づいた手続きを進めることができます。
具体的には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定により、官報に掲載し、立て札を1年間設置して申し出を待ちます。
それでも連絡がなければお墓を整理し、中の遺骨を合祀墓(他の多くの遺骨と一緒に埋葬されるお墓)などに移す「改葬」が可能になります。
公営墓地の場合、撤去費用は税金で賄われるため、予算の都合上すぐには実行されず、長年放置されることもあります。
しかし、民営霊園や寺院墓地では、管理規約に基づいて比較的速やかに手続きが進められることも少なくありません。
また、法的な問題だけでなく、放置されたお墓は雑草が生い茂り、景観を損ねる原因となります。
これは、周辺のお墓を大切に管理されている他の利用者の方々に対して、大変心苦しい状況を生み出してしまいます。
このように、お墓の放置は、ご先祖様にとっても、周囲の方々にとっても、決して望ましい状態とは言えません。
墓じまいをしなくても大丈夫なケースとは
お墓の管理が難しいと感じる方が増える中で、必ずしも全ての人が墓じまいをしなければならないわけではありません。
墓じまいをしなくても大丈夫なケースも存在します。
最も明確なのは、お墓を継いでくれる承継者がいて、その方が責任を持って管理・供養を行える場合です。
兄弟姉妹や親族間で話し合い、今後の管理方法や費用負担について合意が形成できているのであれば、急いで墓じまいを決断する必要はありません。
大切なのは、誰かがお墓を守り続けていくという体制が整っていることです。
お墓がある寺院との関係性によっては、解決策が見つかることもあります。
例えば、寺院が永代にわたって供養を行ってくれる「永代供養墓」を境内に設けている場合があります。
この場合、既存のお墓を撤去(墓じまい)した後、ご遺骨をその永代供養墓に移すことで、管理の負担なく供養を続けていくことが可能です。
寺院によっては、檀家関係を維持したまま比較的安価に移行できる場合もあるため、まずは菩提寺の住職に相談してみるのが良いでしょう。
もうひとつは、お墓自体が山奥にあり、そのままにしておいても誰の迷惑にもならない場合です。
お墓の中の遺骨だけを何処かに移せば、墓石はそのままでもよい可能性もあります。
ただし、これらのケースにおいても、将来的な状況の変化は考えられます。
現時点では大丈夫でも、次の世代、さらにその次の世代まで負担をかけないか、という長期的な視点を持つことが肝心です。
墓じまいしない永代供養という選択肢

「お墓の管理は難しいが、先祖代々のお墓を完全になくしてしまうのには抵抗がある」と感じる方にとって、「墓じまいしない永代供養」は有力な選択肢の一つになり得ます。
これは、現在のお墓を物理的に撤去(墓じまい)し、取り出したご遺骨を、これまでお世話になっていた寺院や霊園が管理する永代供養墓へ移す方法を指します。
この方法の大きなメリットは、お墓の清掃や管理といった物理的・経済的な負担から解放される点です。
また、全く知らない土地の施設に移すのではなく、これまで慣れ親しんだ環境でご先祖様の供養を続けてもらえるという安心感があります。
永代供養にはいくつかの形態があります。
永代供養の主な種類
- 合祀墓(ごうしぼ)
他の多くの人々の遺骨と一緒に、一つの大きな供養塔などに埋葬される形式です。費用を最も抑えられる一方で、一度埋葬すると二度と個別の遺骨を取り出すことはできなくなります。 - 集合墓
一つの大きな墓碑のもとに、個別の骨壺を安置するスペースが設けられている形式です。一定期間(例:33回忌までなど)は個別に安置され、その後は合祀されるのが一般的です。 - 個人墓・夫婦墓
一般的なお墓と同じように個別の墓石を建てますが、承継者が不要で、霊園や寺院が永代にわたって管理・供養をしてくれる形式です。
どの形式を選ぶかによって費用や供養の方法が異なります。
墓じまいをせずに永代供養へ移行することは、物理的なお墓はなくなりますが、供養の心を未来へ繋ぐ一つの形です。
ただし、合祀の場合は後戻りできないため、親族と十分に話し合ってから決めることが大切です。
墓石の処分方法
墓じまいを行う際、撤去した墓石は専門の業者によって適切に処分されます。
ご先祖様の魂が宿っていた墓石ですが、法律上は「産業廃棄物」として扱われるのが一般的です。
処分の流れは、まず僧侶にお願いして「閉眼供養(魂抜き)」という儀式を執り行います。
これにより、墓石は宗教的な意味合いを解かれ、単なる「石」に戻ると考えられています。
その後、石材店などの専門業者が墓石を解体・撤去します。
撤去された墓石は、産業廃棄物の中間処理施設へ運搬されます。
そこでは、巨大な機械によって細かく粉砕処理されます。
粉砕された石は「砕石」となり、再生資材として新たな役割を担うことになります。
例えば、道路工事の際のアスファルトの下に敷かれる路盤材や、建物の基礎工事に使われるコンクリートの骨材など、公共事業や民間工事で幅広く再利用されているのです。
ここで注意すべき点は、不法投棄の問題です。
残念ながら、一部の悪質な業者が解体した墓石を山中などに不法投棄するケースが報告されています。
依頼した側が直接罪に問われることは稀ですが、大切なご先祖様の墓石がそのような扱いを受けるのは避けたいものです。
そのため、業者を選ぶ際には、産業廃棄物処理の許可を得ているか、そして適正に処理したことを証明する「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を発行してくれるかを確認するです。
信頼できる業者を見極める上で非常に重要なポイントとなります。
墓石処分は自分でできるのか
墓じまいを考える際に、費用を少しでも抑えたいという思いから「墓石の処分を自分でできないか」と考える方がいるかもしれません。
しかし、個人が自分で墓石を処分することは、現実的に見て不可能であり、また非常に危険です。
その理由はいくつかあります。第一に、墓石は極めて重い物体です。
小さなものでも数百キログラム、大きなものになると1トンを超えることも珍しくありません。
これを人の力だけで動かしたり解体したりすることはまず不可能です。
クレーンなどの重機や専門的な工具が必要となり、操作には専門知識と技術が求められます。
素人が作業を行えば、重大な事故や怪我に繋がる危険性が極めて高いでしょう。
第二に、墓地は隣接する他家のお墓が密集している場所です。
作業中に誤って隣のお墓を傷つけたり、倒してしまったりした場合、高額な損害賠償問題に発展する可能性があります。
そして第三に、法的な問題があります。
前述の通り、解体された墓石は「産業廃棄物」として扱われます。
産業廃棄物は、許可なく収集・運搬・処分することが法律で禁じられています。
個人が自家用車で運んで処分場に持ち込むこともできません。
適正な処理を行うためには、認可を受けた専門業者に委託する以外の方法はないのです。
以上の点から、墓石の処分は費用がかかるとしても、必ず専門の石材店や解体業者に依頼する必要があります。
安全と法律遵守の観点から、ご自身での作業は絶対に避けてください。
いらなくなった墓石はどうなるのか
墓じまいによって役目を終え、いらなくなった墓石のその後の行方は、多くの方が気になるところでしょう。
大切なご先祖様を祀ってきたものですから、単に捨てられるというイメージには抵抗を感じるかもしれません。
まず、大前提として、墓石は閉眼供養(魂抜き)を経て、宗教的な意味を持つ礼拝の対象から、単なる「石材」へとその性質を変えます。
この儀式を終えることで、心理的な区切りをつけることができます。
その後、石材店によって解体・撤去された墓石は、前述の通り、産業廃棄物として処理されます。
しかし、その多くは単に廃棄されるのではなく、リサイクルという形で有効活用されています。
中間処理施設で細かく砕かれた墓石は、再生砕石として生まれ変わります。
これは、新しい道路の基礎となる路盤材や、建築物のコンクリートの材料などとして、社会のインフラを支える一部となるのです。
ご先祖様のお墓が、形を変えて社会貢献に繋がると考えれば、少しは気持ちが和らぐかもしれません。
一部の寺院や地域では、墓石の中でも「〇〇家之墓」などと刻まれた竿石(さおいし)だけは粉砕せずに、無縁塚などに集めて供養するという慣習が残っている場合もあります。
全ての石材が対象となるわけではありませんが、このような供養の方法を希望する場合は、事前に石材店や寺院に相談してみると良いでしょう。
いずれにせよ、いらなくなった墓石が不適切に扱われることがないよう、信頼できる業者に処分を依頼することが最も大切です.
墓じまい 墓石そのまま再利用する方法と費用

- 墓じまいで墓石再利用はできるのか
- 墓石リメイクと手元供養
- お墓の墓石を撤去する費用の相場
- お金がない場合の対処法
- 補助金は利用できるのか
- 墓じまい 墓石そのままの多様な選択肢
墓じまいで墓石再利用はできるのか
「墓じまいはしたいが、愛着のある墓石を何とか再利用できないか」と考える方は少なくありません。
結論から言うと、墓石の再利用は可能ですが、いくつかの条件や注意点があります。
最も一般的な再利用の方法は、現在のお墓から墓石をそのまま新しい墓地へ移設する「墓石の引越し」です。
この方法のメリットは、先祖代々受け継いできた墓石を引き続き使えるため、故人への想いを繋いでいける点にあります。
また、新しく墓石を購入する費用がかからないため、場合によってはコストを抑えられる可能性もあります。
しかし、デメリットや注意点も存在します。
まず、移転先の墓地が墓石の持ち込みを許可しているかを確認する必要があります。
霊園によっては指定石材店制度があり、外部からの墓石の持ち込みを禁止している場合があります。
次に、物理的な寸法の問題です。
新しい墓地の区画サイズが現在の墓石や外柵(お墓の周りの囲い石)と合わないケースがほとんどです。
その場合、石材をカットしたり加工したりする必要が生じ、追加の加工費がかかります。
墓石の運搬費用も考慮しなくてはなりません。
特に遠方への引越しの場合、運搬費と加工費を合わせると、結果的に新しいお墓を建てるよりも費用が高くついてしまうこともあります。
墓石の状態も重要です。
長年の風雨で劣化が進んでいる場合、移設作業中に破損するリスクもあります。
石材店とよく相談し、費用やリスクを総合的に判断した上で、再利用するかどうかを決定することが賢明です。
墓じまい後の墓石リメイクと手元供養
墓じまいをした後、大きな墓石は不要でも「ご先祖様の生きた証を何らかの形で残したい」という想いに応える選択肢として、墓石のリメイクや手元供養が注目されています。
墓石のリメイクとは、解体した墓石の一部を利用して、新しい記念品や石造物を作り直すことです。
例えば、墓石の最も主要な部分である竿石(さおいし)を小さく加工して、ご自宅の庭に置けるサイズの石碑や地蔵、あるいは記念のプレートや表札などに生まれ変わらせることができます。
これにより、大規模な墓地の管理は不要になりながらも、手を合わせる対象を身近に置くことが可能です。
一方で、手元供養は、ご遺骨の一部を自宅など身近な場所に保管して供養する方法です。
この手元供養品の一つとして、遺骨アクセサリーがあります。
ご遺骨を細かく粉末状にし、ペンダントやリング、ブレスレットなどに納めることで、故人を常に身近に感じることができます。
ただし、遺骨アクセサリーについては様々な意見があることも知っておくべきでしょう。
カルティエやティファニーといった、いわゆるハイブランドが遺骨専用のアクセサリーを製造・販売しているわけではありません。
一般的には、遺骨を納めるために作られた専用のアクセサリーか、写真などを入れるロケットペンダントに遺灰や粉末状にしたご遺骨を少量納める形になります。
これを身に着けることで心が安らぐと感じる方がいる一方、「いつまでも故人への想いを引きずってしまい、気持ちの整理が進まない」「紛失するリスクが怖い」といった理由から、持たない方が良いという意見もあります。
墓石のリメイクや遺骨アクセサリーは、故人を偲ぶ新しい形ですが、ご自身の気持ちやライフスタイル、そしてご家族の意見も踏まえ、慎重に検討することが大切です。
お墓の墓石を撤去する費用の相場
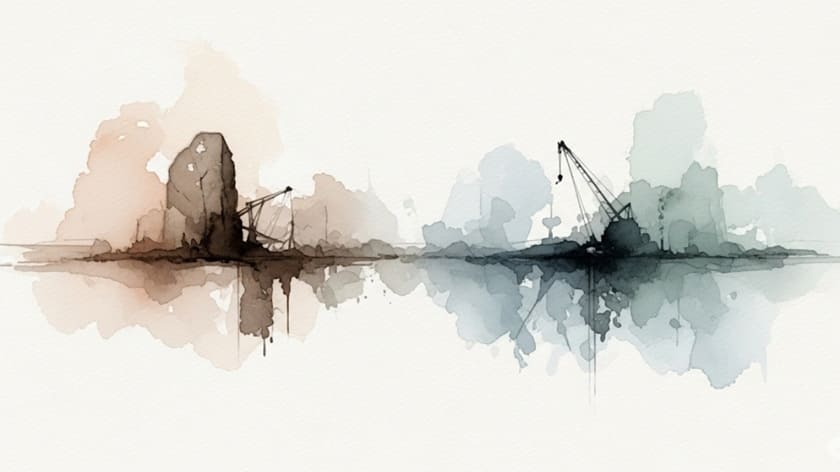
墓じまいを決断した際に、最も気になるのが費用面でしょう。
特にお墓の墓石を撤去するための費用は、墓じまい全体のコストの半分以上を占める要素です。
墓石の撤去費用の相場は、一般的に1平方メートルあたり8万円~15万円程度が目安とされています。
しかし、これはあくまで目安であり、お墓の状況によって金額は大きく変動します。
費用が変動する主な要因は以下の通りです。
- 墓地の立地
クレーン付きのトラックが墓地のすぐそばまで入れるか、あるいは通路が狭く手作業で運び出す必要があるかによって、人件費や作業時間が大きく変わります。山間部や階段が多い場所では、費用が高くなる傾向にあります。 - 墓石の大きさや石の量
墓石が大きかったり、外柵や灯篭など石材の量が多かったりすると、解体・運搬の手間が増えるため費用は上がります。 - 基礎工事の有無
地中にコンクリートの基礎が打たれている場合、それを解体・撤去する「はつり作業」が必要となり、追加費用が発生します。
これらの工事費用に加えて、別途必要となる可能性のある費用も考慮しておかなくてはなりません。
| 項目 | 費用相場 | 備考 |
| 墓石の解体・撤去費用 | 8万円~15万円/㎡ | 立地や墓石の大きさで変動します。 |
| 閉眼供養のお布施 | 3万円~10万円 | 儀式を執り行う僧侶へのお礼です。寺院との関係性によります。 |
| 離檀料 | 0円~20万円程度 | 寺院の檀家をやめる際に必要となる場合があります。感謝の気持ちとして渡すもので、法的な義務はありません。 |
| 行政手続き手数料 | 数百円~1,500円程度 | 改葬許可証の申請などに必要な実費です。 |
| 新しい納骨先の費用 | 数万円~数百万円 | 永代供養、散骨、新しいお墓の建立など、選択肢によって大きく異なります。 |
最終的な総額を知るためには、複数の石材店から見積もりを取る「相見積もり」が不可欠です。
見積書の内訳をしっかりと確認し、納得のいく業者に依頼することが、後悔のない墓じまいの鍵となります。
墓じまいにお金がない場合の対処法
「墓じまいをしたいけれど、まとまったお金がない」という悩みは、決して珍しいことではありません。
墓じまいには数十万円単位の費用がかかるため、すぐに用意するのが難しい場合もあるでしょう。
そのような状況に直面した際の対処法をいくつかご紹介します。
まず考えられるのは、支払い方法の相談です。
依頼する石材店によっては、費用の分割払いや、提携している信販会社の「メモリアルローン」を利用できる場合があります。
全ての石材店が対応しているわけではありませんが、見積もりを依頼する際に、支払い方法についても相談してみる価値はあります。
次に、親族間で費用を分担する方法です。
お墓は、たとえ名義人が一人であっても、多くの親族にとって大切な場所です。
墓じまいをせざるを得ない事情を丁寧に説明し、費用の一部を負担してもらえないか相談してみましょう。
お盆や法事など、親族が集まる機会に話し合いの場を設けるのが良いかもしれません。
事前に墓じまいにかかる費用の見積書を用意しておくと、話がスムーズに進みやすくなります。
また、公的な制度として、自治体が低所得者世帯向けに設けている「生活福祉資金貸付制度」があります。
これは、冠婚葬祭などの一時的な出費に対応するための貸付制度ですが、利用には収入などの厳しい審査条件があります。
墓じまいの費用として必ず利用できるとは限りませんが、他に手段がない場合は、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してみるのも一つの手です。
いずれにしても、費用がないからといってお墓を放置してしまうのが最も避けるべき事態です。
まずは信頼できる石材店や親族に相談し、解決の糸口を探ることが大切になります。
墓じまいに補助金は利用できるのか

墓じまいの費用負担を少しでも軽減したいと考えたとき、「国や自治体からの補助金は利用できないのだろうか」という疑問が浮かぶかもしれません。
結論から申し上げますと、2025年現在、国が設けている全国一律の墓じまい補助金制度は存在しません。
墓じまいは、基本的には個人の家庭の事情と見なされるため、公的な補助の対象とはなりにくいのが現状です。
ただし、ごく一部の地方自治体では、独自の補助金制度を設けているケースがあります。
これらの制度は、主に管理されずに放置された「無縁墓」が増えることを防ぐという、公的な目的のために実施されています。
例えば、過去には千葉県市川市や群馬県太田市などで、墓地使用者を対象とした墓石の撤去費用の一部を助成する制度がありました。
しかし、これらの制度は非常に稀な例であり、多くの自治体では実施されていません。
また、制度があったとしても、以下のような厳しい条件が設けられていることがほとんどです。
- その自治体に長期間居住していること
- 自治体が管理する公営墓地の使用者であること
- 税金の滞納がないこと
- 一定期間、墓地管理料を納付していること
このように、補助金制度を利用できる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
最も確実な方法は、ご自身がお墓を構えている市区町村の役所の担当窓口(生活衛生課など)に、墓石の撤去に関する助成制度の有無を直接問い合わせてみることです。
補助金を当てにするのではなく、基本的には自己資金で賄うものとして計画を立てるのが現実的でしょう。
まとめ:墓じまいして墓石をそのままにできる?
ここまで、墓じまいと墓石の扱いについて様々な角度から解説してきました。最後に、この記事でご紹介した重要なポイントをまとめます。
- 田舎の墓などを放置すると無縁仏として撤去される可能性
- 承継者がいて管理が可能なら墓じまいをしなくても大丈夫
- 墓じまいをせず同じ寺院の永代供養墓に移す選択肢もある
- 閉眼供養後の墓石は産業廃棄物として専門業者が処分する
- 墓石の処分は危険と法律の問題から自分では行えない
- 撤去された墓石は砕石としてリサイクルされ社会で再利用される
- 墓石の再利用は新しい墓地の寸法や規定が合えば可能
- 墓石の移設は運搬費や加工費で新品より高くなることもある
- 墓石の一部を加工して小さな記念碑などにリメイクできる
- 遺骨を納めるアクセサリーでの手元供養という方法もある
- 遺骨アクセサリーには気持ちの整理が進みにくいという意見もある
- 墓石撤去費用の相場は1㎡あたり8万~15万円が目安
- 墓じまいにお金がない場合は分割払いや親族間での分担を相談する
- 国の墓じまい補助金制度はなく自治体の制度も極めて稀である
- 墓石をそのままにする選択肢は一つではなく多角的な検討が大切
厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要
