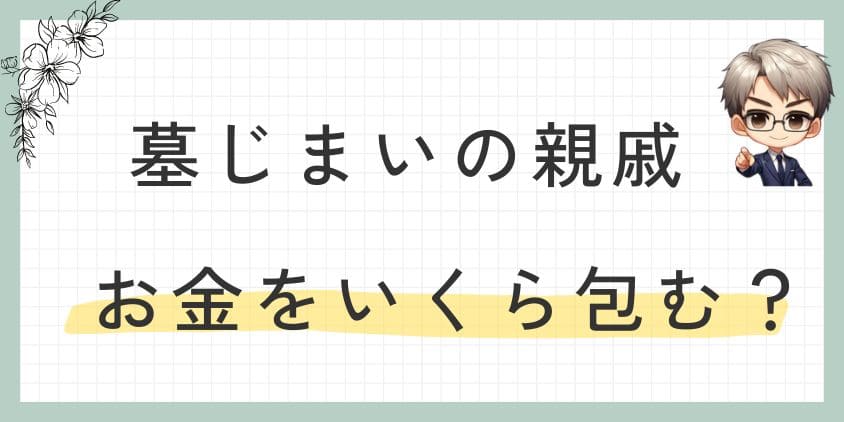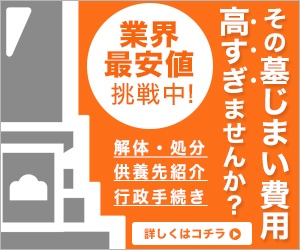「墓じまいに呼ばれたら?」
「表書きは御香典?御仏前?」
「いくら包む?」
墓じまいに呼ばれた時の表書きと金額について、わかりやすく解説します。
法事に呼ばれた時の表書きは、香典とかお布施、御供、御霊前、御仏前などがあります。
でも、墓じまいでどれを使って良いのか迷ってしまいますよね。
この記事では、墓じまいで使われる表書きとその金額やマナーなどについて解説します。
また、親戚や兄弟でお金は違うのか、費用は払うのか、服装は?などの疑問にお答えします。
ただし、地域によって違いがありますので、最終的には住職や親戚に確認してください
- 墓じまいのお金の表書きと金額
- お香典などの親戚が支払うお金
- 墓じまいにかかる費用
- 費用を抑えるための方法
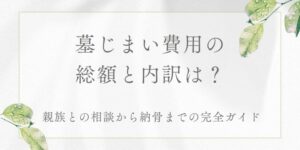
墓じまいに親戚が包むお金の表書きは何?金額は?
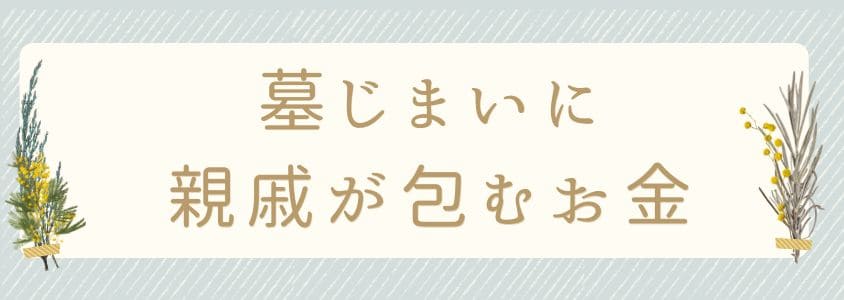
- 何に参列するかによって変わる
- 閉眼供養に参列するときの表書きと金額
- 撤去工事に参列するときの表書きと金額
- 開眼法要(建碑式)に参列するときの表書きと金額
- 納骨式に呼ばれた時の表書きと金額
- お布施は祭祀承継者が払う
- 墓じまいに御香典は使ってはダメ
- 費用を負担は兄弟まで?親戚が費用を負担するときも
何に参列するかによって変わる
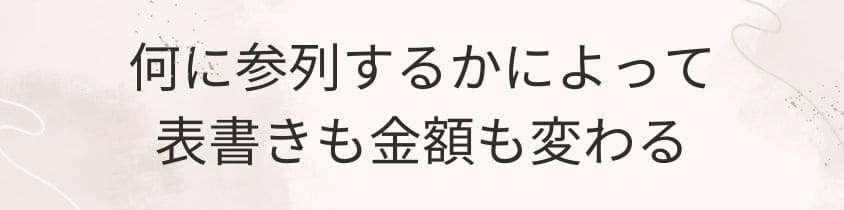
墓じまいと一言でいってもいろいろなことをやります。
祭祀承継者に包んでいくお金も、呼ばれる内容で変わってきます。
| 内容 | 表書き | 金額 |
|---|---|---|
| 閉眼供養 | 御供 | 1~3万円 |
| 撤去工事 | 御供 | 0.5~1万円 |
| 開眼法要 | 建碑祝 | 1~3万円 |
| 納骨式 | 御仏前 | 0.5~3万円 |
金額は祭祀承継者との関係性や、墓じまい費用への援助の有無、新しい供養先、住んでる地域によって変わります。
一緒に呼ばれていく人や、詳しい高齢者にまずは相談するのがおすすめです。
また、1日ですべて行われることは少ないので、組み合わせによって表書きが変わっってきます。
- 閉眼+撤去 ⇒ 御供
- 閉眼+撤去+納骨 ⇒ 御仏前
- 全部 ⇒ 御供、御仏前
慶事と弔事が続けて行われるときには、弔事のルールが優先されます。

1つずつ詳しくみていきます
閉眼供養に参列するときの表書きと金額
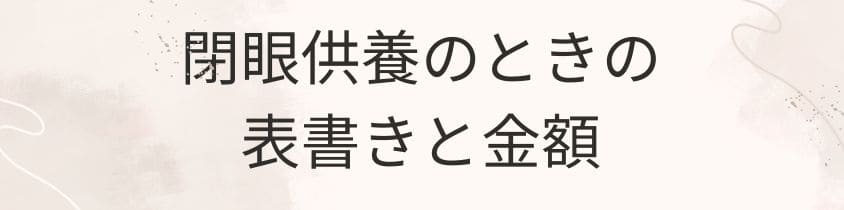
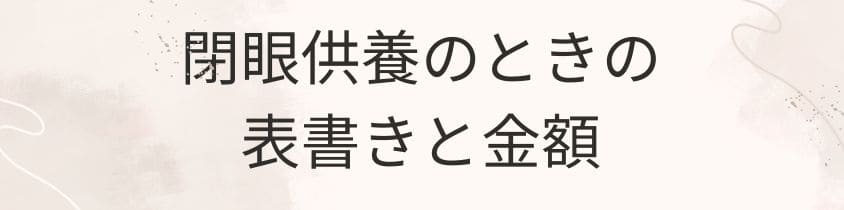
閉眼供養に行くときの表書きは「御供」で、1~3万円位包み、祭祀承継者に渡します。
黒白水引の不祝儀袋で、濃い黒ペンで書きます。(関西は黃白)
そのあとにすぐ撤去工事をやるときが多く、「御供」は1つで大丈夫です。
撤去工事の後に会食をすることは少なく、服装も略式礼装(地味な平服)で大丈夫です。
撤去工事に参列するときの表書きと金額
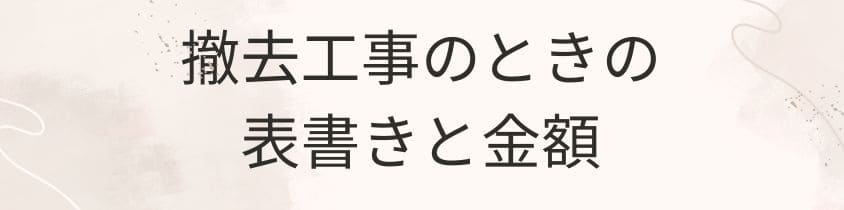
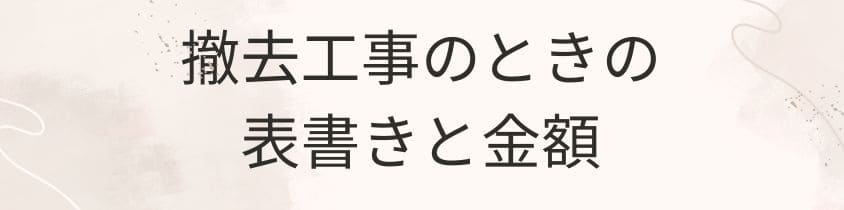
撤去工事だけに呼ばれるのはかなり少ないです。
多くの墓じまいでは、閉眼供養に引き続き行われます。その場合は「御供」です。
新しい供養先が同じ場所なら、そのまま納骨式まで行われる場合もあります。その場合は「御仏前」です。
撤去工事だけなら「御供」で、地味な平服でいけば大丈夫です。



呼ばれていく人同士で相談しましょう
開眼法要(建碑式)に参列するときの表書きと金額
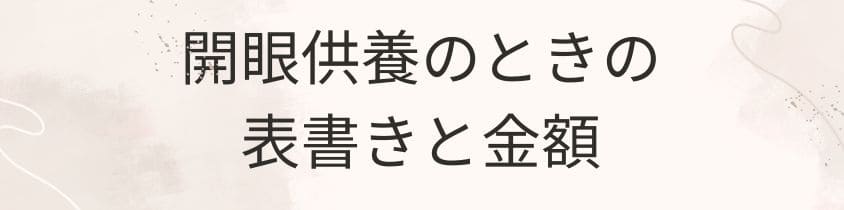
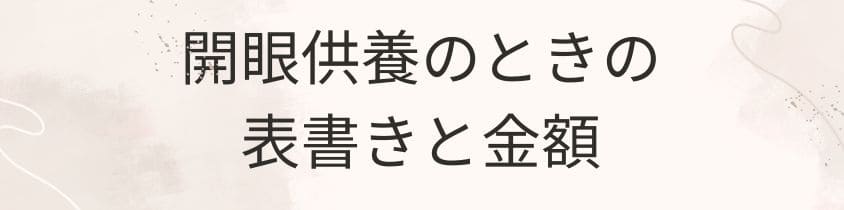
新しいお墓を立てた時には建碑式が行われ、開眼供養をしてもらいます。
その場に呼ばれたときは、お祝いごとなので表書きは「建碑祝」「建碑設立御祝」で、紅白水引がついた祝儀袋に新札を入れて、濃い黒ペンで書きます。
金額は一般的に5千円〜3万円程度が多いです。



お墓を立てるのはお祝いなんだね
ただし、同日に閉眼供養とか納骨法要が行われるときには、弔事が優先となり、お祝い金ではなく「御供」となります。
納骨式に呼ばれた時の表書きと金額
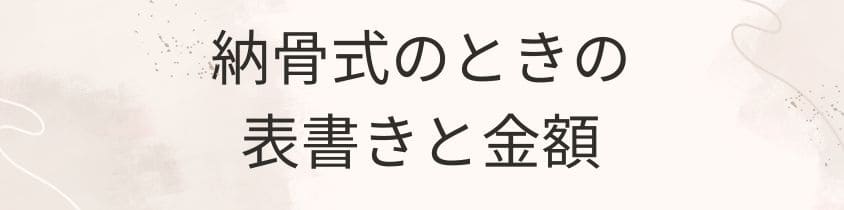
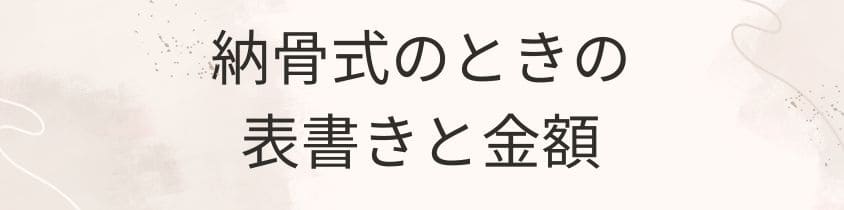
納骨式に呼ばれたときの一般的な表書きは、「御仏前」です。
地域や関係性によって異なりますが、金額は5千円~1万円くらいです。
黒白の水引の不祝儀袋を使い、濃い黒ペンで書きます。
納骨式の後に会食がある場合、プラス1万円くらい包みます。
お布施は祭祀承継者が払う
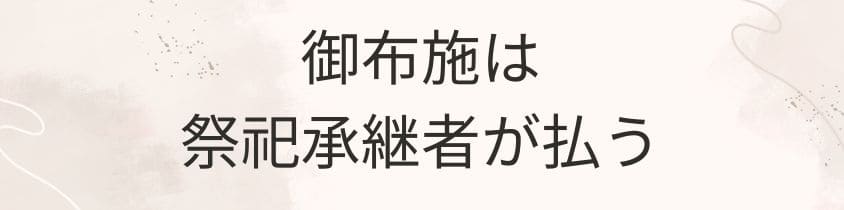
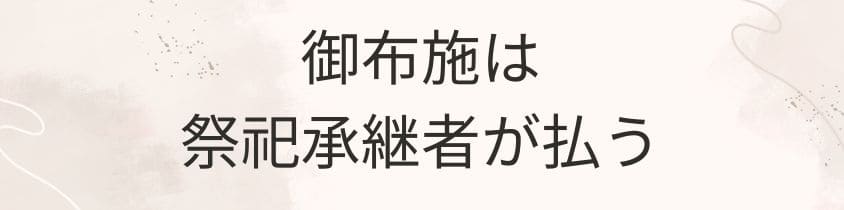
住職にお経をあげて貰う時に必要なのが、お布施です。
お布施は祭祀承継者が住職に払うもので、親戚がお布施を直接支払うことはありません。
お布施はお寺への感謝の気持ちとして支払われるものだからです。
親戚としては、祭祀承継者に一任して関わらないのが一般的です。



祭祀承継者って大変・・・
墓じまいに御香典は使ってはダメ
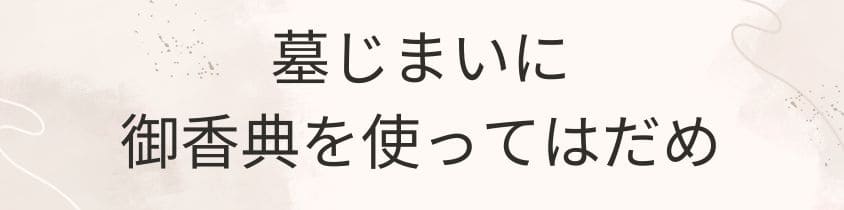
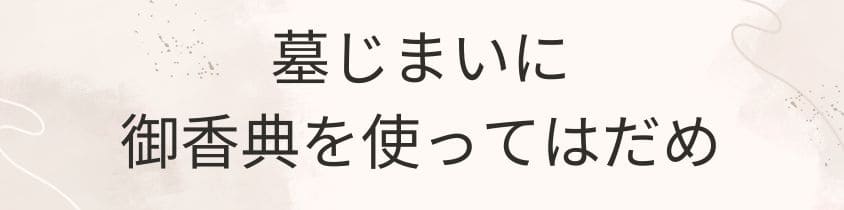
お葬式でよく見るものに、「御香典」「御香料」「御弔料」などがあります。
そういった香典は葬儀や法要の際に、亡くなった方への供養として渡されるものです
なので、墓じまいの際には、「御香典」「御香料」「御弔料」などは使ってはいけません。
墓じまいの際には、「御供」か「御仏前」です。
費用負担は兄弟まで?親戚が費用を負担するときも
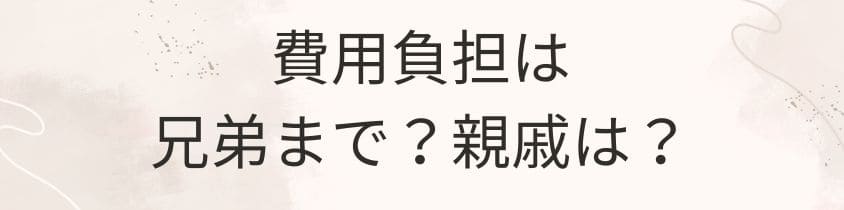
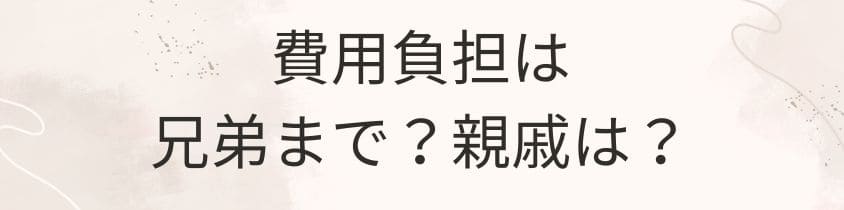
墓じまいの費用は、祭祀承継者が負担することが一般的ですが、親戚が一部負担しているケースもあります。
特に費用が高額な場合は、親戚間で分担する傾向が多いです。
親戚が支援金として費用の一部を負担したり、祭祀承継者の兄弟だけが支援金を出している場合も多く、その地域やご家庭によって違います。
墓じまいする前には、祭祀承継者としっかりと話をしておくのが大切です。
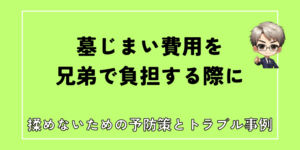
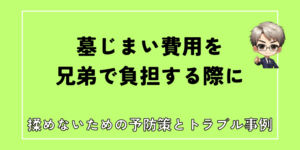
墓じまいの時の親戚のお金に関するナレッジ
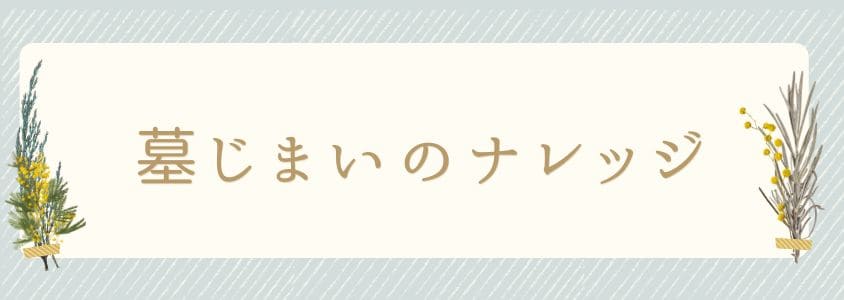
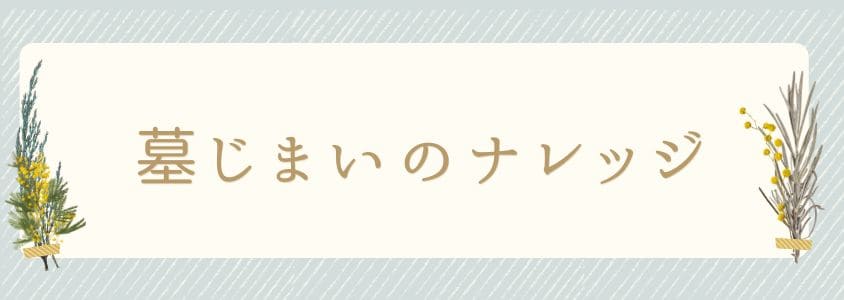
墓じまいを円滑にするちょっとしたコツや豆知識を紹介します。
- 何に参列するかによって服装も違う?
- 親戚への連絡はどうする?
- 費用を生前に用意する
- 費用負担を親族にお願いするのもあり
- 御供や御仏前にお返しは?
- 石屋さんへのお礼はする?しない?
- ローンするくらいなら、やらない!
- 費用の負担割合は曖昧な点を残さない
- 墓じまいの費用を抑えるのが一番!
- おすすめの代行業者3選
何に参列するかによって服装も違う?
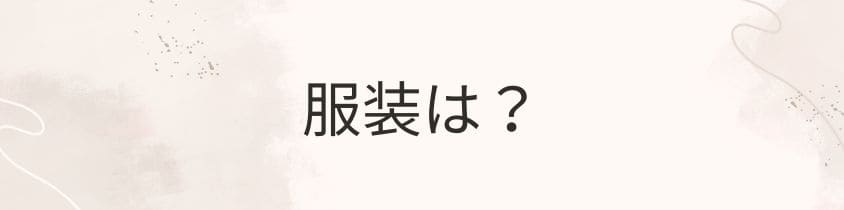
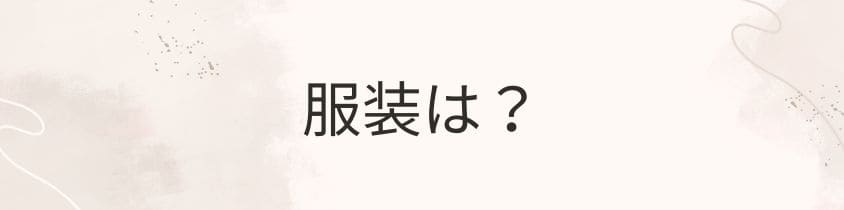
何に呼ばれたかによって、着ていく服装が少し違います。
| 行事 | 慶弔 | 服装 |
|---|---|---|
| 閉眼供養 | 弔事 | 準喪服 |
| 撤去工事 | 弔事 | 略式礼装 |
| 開眼供養 | 慶事 | 準礼服 |
| 納骨式 | 弔事 | 準喪服 |
準喪服とはいわゆる礼服で、ブラックスーツやブラックフォーマルです。
男性の略式礼装(略喪服)とは、ブラックスーツやダークスーツ(濃いネイビー、チャコールグレーなど)です。
女性の略式礼装(略喪服)は、カジュアルすぎないワンピースやアンサンブルなどで、濃紺やグレーといった地味な配色であれば問題ありません。。
弔事のときのネクタイは、ダークカラーで光沢や柄の少ないものをつけます。
慶事のときのネクタイは、結婚式と同じようにシルバーグレーか淡く明るい色のカラーネクタイです。黒色はNGです。
閉眼供養に呼ばれていく時に、よく「平服でいいです」と言われます。
平服とはカジュアルな服ではなくて略式礼装(略喪服)のことで、「平服で」と言われたら略喪服を着ていきましょう。



祭祀承継者(喪主)はいつでも喪服が好ましいです
親戚への連絡はどうする?
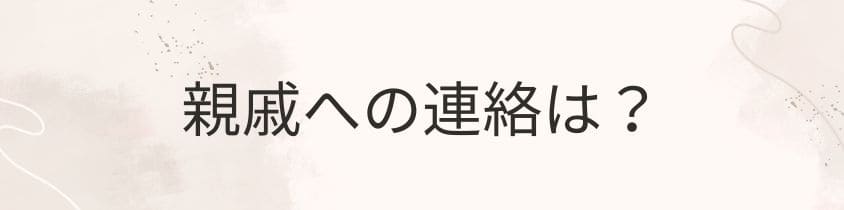
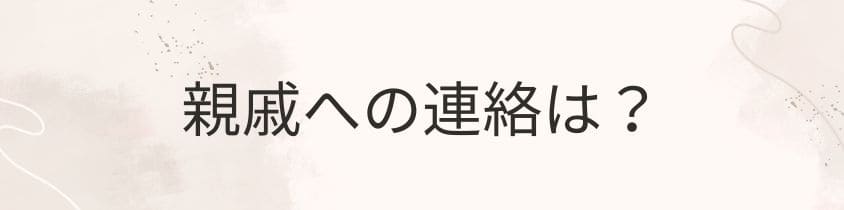
墓じまいの親戚への連絡は、墓じまいの前と後の2回で行うのがおすすめです。
墓じまいの前とは、まだ工事をする前です。相談しなかった親戚にもはがきで伝えておけば、不要なトラブルを避けられます。
墓じまいの後は、納骨完了の1ヶ月後くらいに、はがきで出せばOKです。
付き合いがあるかどうかはともかく、親戚だという認識があれば、はがきで一報だけは入れておいたほうが無難です。



墓じまい後のトラブルの1位は親族です
費用を生前に用意する
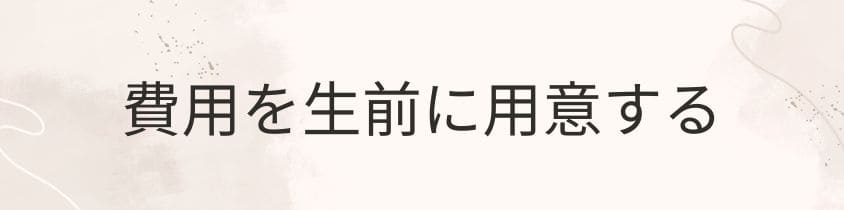
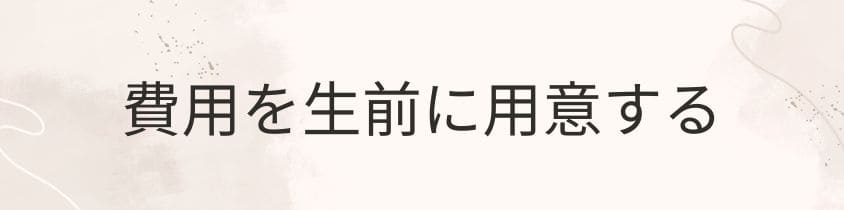
生前に墓じまいの費用を用意しておくのは、祭祀承継者や親族の負担を軽減するために非常に重要です。
生前に資金を確保することで、遺族が急な出費に困るのを避けられます。
生前に計画すれば、親族間のトラブルを防ぎスムーズに墓じまいできます。
生前に費用を用意することで、遺族の負担を軽減し、計画的に進められます。



生前に用意するなら、やれよ!という意見も w
費用負担を親族にお願いするのもあり
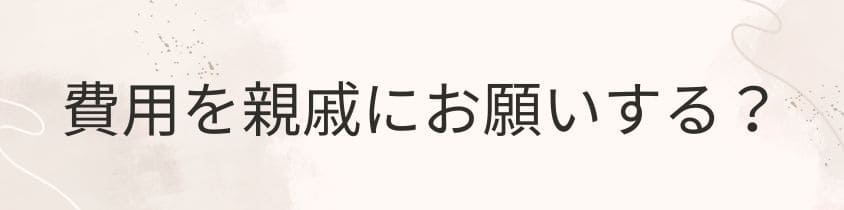
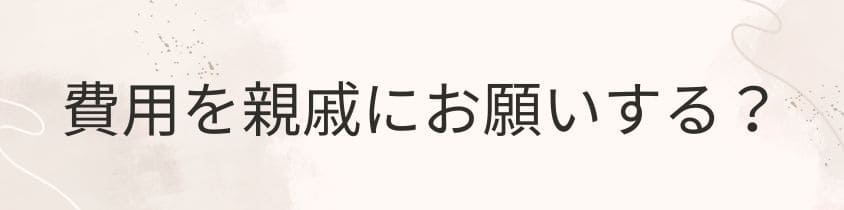
墓じまいの費用を親族にお願いすることは、とても有益な一つの方法です。
特に費用が高額になる場合、ひとりだけで進めようとすると、親族間でトラブルになる傾向が高いです。
お墓を守るのは祭祀承継者ひとりですが、お金の支援割り振りで全員に共通のコンセンサスを得られます。
費用負担を分担すると同時に、責任感も分けられて、スムーズに墓じまいを進めることができます。



お金ないから・・・お願い!
御供や御仏前にお返しは?
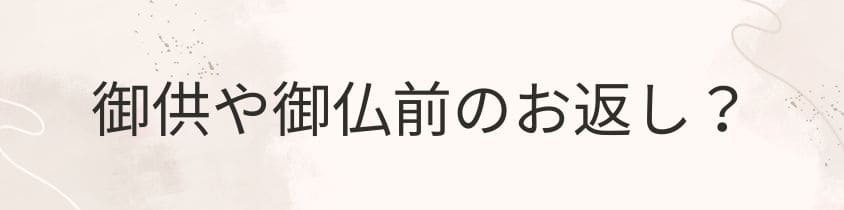
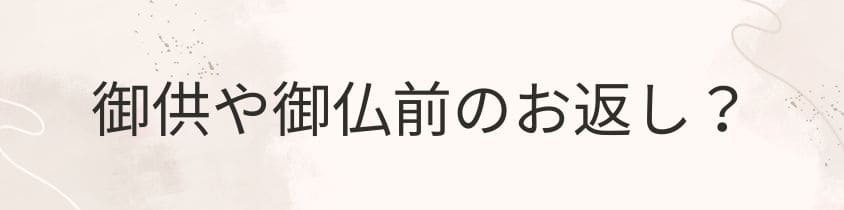
御供や御仏前でお金をもらったら、半額返しをします。
カタログギフトを使う方が多いです。
のしは黒白または双銀の水引で結び切り、表書きは「志」または「粗供養」、その下に祭祀承継者の苗字または〇〇家です。
くわしい内容はギフトショップと相談してみてください。



もらったら返す・・・当たり前ですね
石屋さんへのお礼はする?しない?
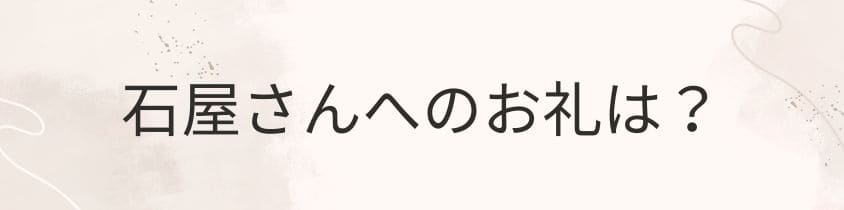
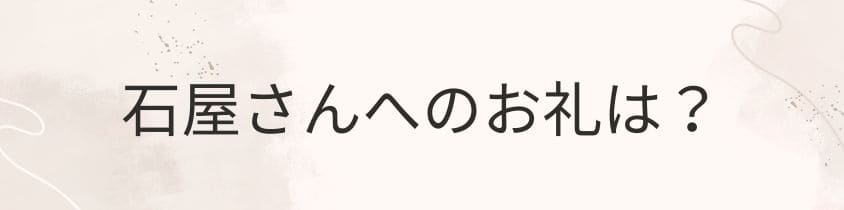
むかしは心付けといって、工事をする人たちにポチ袋などに1000円くらい入れて渡していました。
今は、そういう事も含めて金額を請求されてるはずなので、あえて渡さなくても良いのではないでしょうか。



結婚式なんかとは違いますからね!
ローンするくらいなら、やらない!
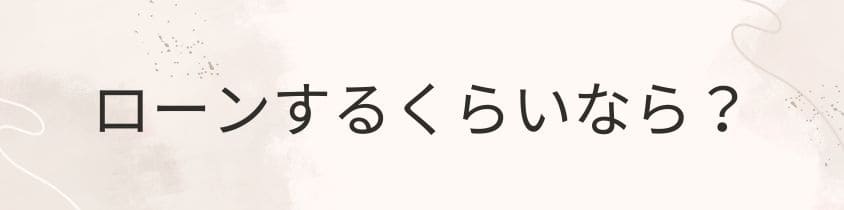
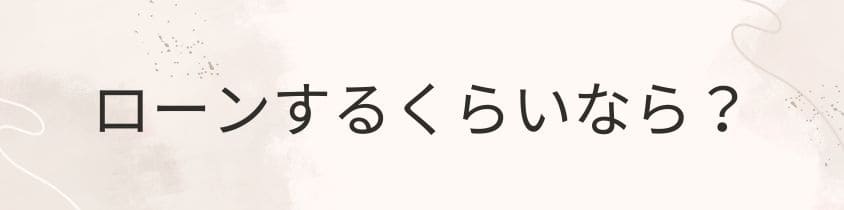
墓じまいの費用をローンで支払うことは避けるべきです。
ローンを組むくらいなら、墓じまいなんかせずに現状のまま維持していくほうが賢いです。
子孫が誰もいなくなり、無縁墓になって困るのはお寺だけだからです。
ローンを組むくらいなら、墓じまいを延期する方が望ましいです。



生きてる人の生活を優先させましょう
費用の負担割合は曖昧な点を残さない
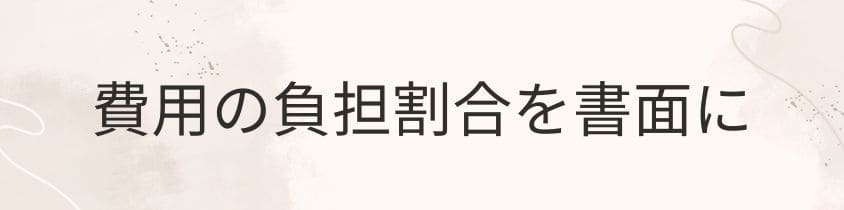
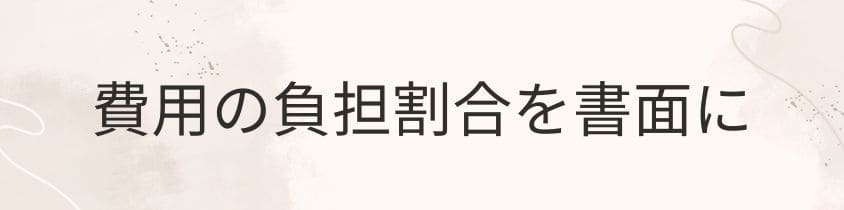
墓じまいの費用の支援を親族たちにお願いしたら、曖昧な点を残さないように明確に決めておきましょう。
決めたら、書面に残してコピーをみんなで共有するのが望ましいです。
あとから、「言った」「言わない」の不毛な論争も防げますし、余分に費用がかかったときにも対処できます。
あとから感謝するためにも、負担割合をしっかりと書面に残しておきましょう。



後期高齢者は忘れっぽいですからね
墓じまいの費用を抑えるのが一番!
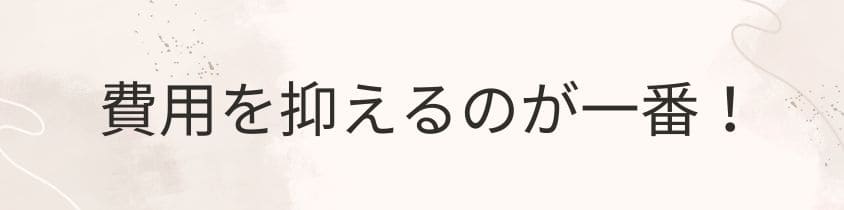
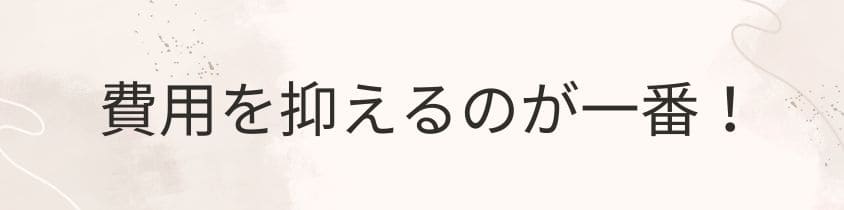
墓じまいの費用で、親族間でもめないためには、費用自体を抑えるのが大切です。
費用を抑えるためにできるのは3つです。
- 業者に相見積もりを取る
- なるべく安い供養先を選ぶ
- お寺や石材店と良い関係を結ぶ
工事業者を複数比較して安価な業者を選んだり、手元供養や散骨など、費用のかからない供養方法の検討が有効です。
また、お寺や石材店となるべく仲良くなって、融通を利かせてもらうのも良い方法です。
墓じまいの費用を抑えれば、無理なく手続きを進められます。



代行業者を使えば、費用を抑えて時間や手間も節約できます
おすすめの代行業者3選
秋田県で墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。
「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から


「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。
サービス内容はこちら。
- お墓の撤去
- 離檀代行・サポート
- 行政手続きサポート
- 撤去業者持ち込み交渉
- 墓じまい全体のサポート
離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。
サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。
安心・安全の「イオンの墓じまい」


日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。
基本的なサービスがワンセットになっています。
- 行政手続き
- お骨の取り出し
- 墓石の解体・処分
- 墓地を更地に戻す
- お骨の受け渡し
公式サイトから詳細の金額をご確認ください。
\ 無料相談はこちら /



イオンカードも使えます
すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」


面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。
サービス内容はこちら。
- 行政手続き代行
- ご遺骨の取り出し
- 墓石の解体・処分
- 墓所の変換
行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。
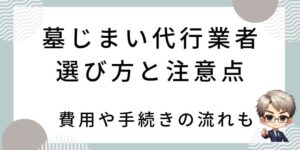
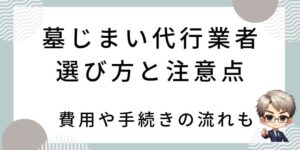
まとめ:【墓じまいに呼ばれた親戚】包むべきお金の相場と表書き
この記事のまとめです。
- 墓じまいの表書きは「御供」や「御仏前」
- 一般的には1万〜3万円程度
- 閉眼供養と撤去工事には「御供」
- 開眼法要には「建碑祝」
- 納骨式の表書きは「御仏前」が一般的
- 地域や宗派によって違うので、事前確認が必要
- 納骨式の金額は5千円〜1万円程度が目安である
- 金額は祭祀承継者との距離感による
- お布施は祭祀承継者が負担
- 墓じまいには「御香典」などは使わない
- 墓じまいの費用は祭祀承継者が負担する
- 親戚が一部を負担することもある
- 墓じまいの費用は30~300万円くらい
- お寺へのお布施は閉眼供養の時に払う
- 新しい供養先の費用は3~200万円
- 工事業者を複数比較することが重要
- 費用を生前に用意しておくのもあり
- 負担割合は曖昧にせず明確に決めて書面に残す



最後まで読んでいただきありがとうございました!
厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要