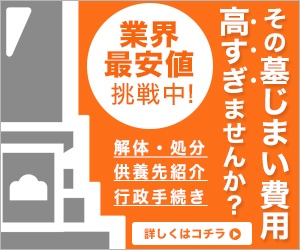「樹木葬で失敗したくない」
「樹木葬って危険なの?」
「墓じまいして樹木葬にしたいけど」
墓じまいして樹木葬にする時に、失敗しないためのたった一つの方法は、下準備をしっかりとすることです。
そもそもですが、「失敗したな~」とか「後悔している」と思うのは生きている人間です。つまり、あなたです。
遺骨になってる人はなにも思わないし、感じません。成仏できないなんてこともないです。
なので故人ではなく、あなたが樹木葬をどう思うのか、親戚や家族がどう感じるのかがとても大切です。
また、多くの人が失敗したと感じるのは、自分が思い描いていたものと実際の結果が異なり、しかもその状況がやり直し不可能であるときです。
つまり、あなたの想像と現実のギャップが大きければ大きいほど、「失敗した」「トラブル」と感じてしまうんです。
そうならないためには、具体的な失敗例や樹木葬の欠点、実態を参考にして、樹木葬の下準備をしっかりするのが大切です。

この記事では、樹木葬の失敗例と具体的な対処法を詳しく解説します
- 樹木葬で実際に起こり得る失敗やトラブル
- 樹木葬の実態と理想のギャップが生む後悔の原因
- 樹木葬の管理体制や供養の違いがもたらすリスク
- 樹木葬の選び方や後悔しないためのポイント
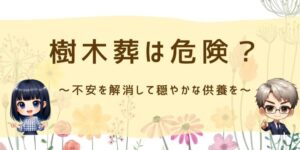
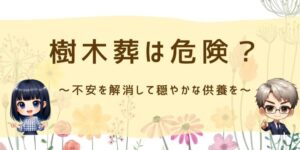
樹木葬の失敗例を16件。具体的に徹底解説
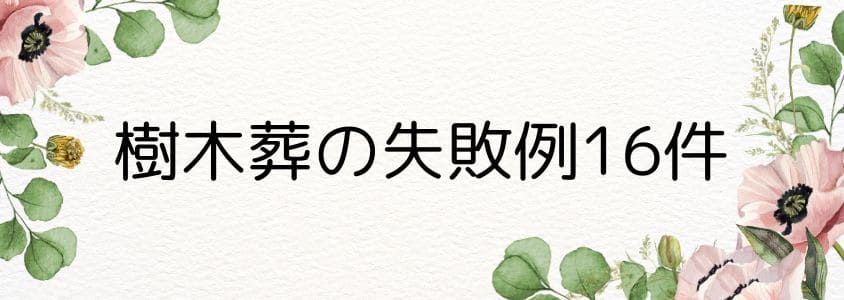
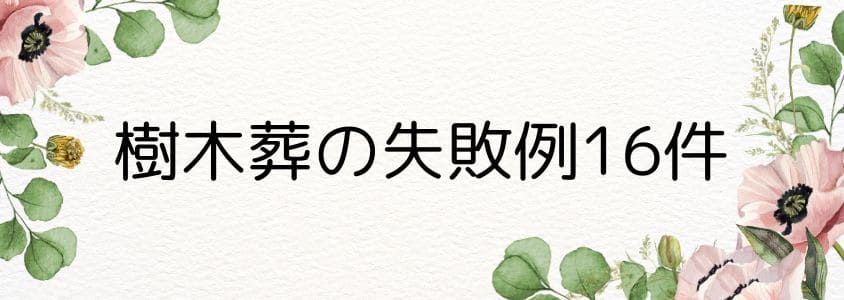
はじめに、樹木葬の失敗の具体例を、16ケース紹介します。
- 実は、自然には還れていなかった
- 成仏できないんじゃないかという不安
- 別々の場所になった、一人用だった
- 考えていたよりも費用が高かった
- お墓参りが思っていたのと違った
- 1墓に1本の樹木じゃなかった
- 景観の変化で後悔
- 広告の見た目と現実の違い
- 管理不足で荒廃
- アクセスが不便
- 虫の多さが問題
- 家族や親族の反対
- 墓地管理の破綻
- ペット埋葬の制約
- 合葬の抵抗感(満員電車の感覚)
- 契約期間の延長とその後の合葬
実は、自然には還れていなかった
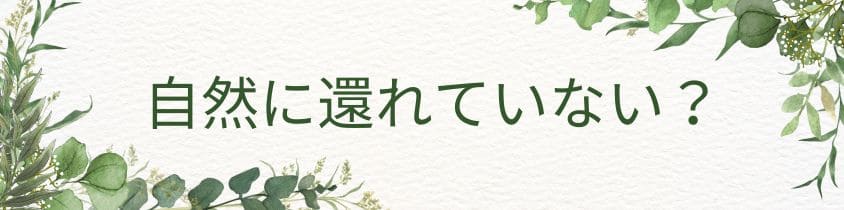
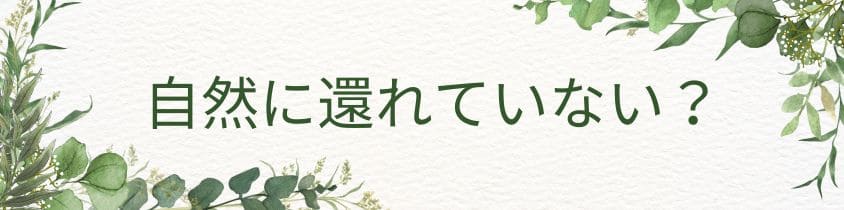
樹木葬の特徴の一つに、「自然に還る」というポイントが挙げられます。
多くの方がそれを信じて樹木葬にされていますが、思ってたイメージと違ったと言われる方が多いです。
実は、遺骨は樹木葬で自然には還っていないんです。
理由は2つです。
- 実はコンクリート納骨も多い
- 火葬された遺骨が土に還るには数百年以上かかる
実はコンクリート納骨も多い
樹木葬と聞くと、自然の中にそのまま遺骨を埋葬し、やがて木や草花に還るというイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし、実は多くの樹木葬では遺骨を直接土に埋めるのではなく、コンクリートの納骨室に収める形式が採用されています。
この形式では、遺骨がコンクリートに囲まれているため、土に還ることはないです。
「自然に還る」と思われてるのは、自然の中に埋葬されるというイメージとごっちゃになってるからです。



企業のイメージ戦略です
火葬された遺骨が土に還るには数百年以上かかる
そもそもですが、火葬された遺骨が自然に還るまでには、数百年という非常に長い時間がかかります。
火葬された遺骨は高温で焼かれるため、表面がセラミック状の硬い層になるからです。
骨自体もとても硬いもので、たとえばエジプトのミイラとか原始人の骨、化石のように、環境さえ整えれば、今でも残ってしまうほど硬いです。
「自然に還る」という樹木葬の理念に魅力を感じていればいるほど、この現実は大きなギャップとなり、ショックを感じられるかもしれません



樹木葬が流行りだした20年前の遺骨は、まだそのままの形のはずです
土葬は数十年~100年で土に還る
一方、土葬の場合は火葬に比べて遺骨が土に還るスピードが速いとされています。
速いと言っても、環境条件によりますが数十年から100年程度で土に還ると言われています。
土中の微生物や昆虫が遺骨を分解し、自然に戻る過程を助けるためです。特に湿潤で微生物の多い環境では、遺骨の分解が促進されます。
ただし、日本では土葬が許可されている地域が限られているため、火葬率は99.99%で、ほとんどの方が火葬されます。



そう簡単には土には還らないということですね
それでも自然に還りたいのなら?
なので、樹木葬は「自然に還る」というキャッチフレーズで多くの方の関心を引いていますが、思われてるイメージと現実は違います。
実際にはまず無理だと思っておいたほうが良いです。
ただし、「本当に自然に還る」という方法もないわけではないです。
自然に還りやすくするためには、遺骨をもっと細かくパウダー状にします。
遺骨をパウダー状にすると、土中の微生物や植物の根によってより早く吸収されます。
実際に、骨の主成分であるリン酸カルシウムは肥料としても使われている成分ですので、植物にとっては栄養分の一部となります。
水に溶けるくらいまでに微生物によって分解されないと、植物に吸収されるまでの時間が非常に長くなります。
さらに、パウダー状にした遺骨を土とよく混ぜます。
混ぜる際には土壌の環境にも配慮します。
酸性が強すぎたり、乾燥しすぎている土壌では、遺骨がうまく分解されません。
遺骨を混ぜる土は適度に湿り気があり、微生物が活発に働ける環境であることが望ましいです。
特に、堆肥や腐葉土などと一緒に混ぜると、微生物の活動が促進され、遺骨の分解がよりスムーズに進むでしょう。
このように、畑の土を作るような感覚で作業しないと、「自然に還る」のは難しいです。



どうしても早く自然に還りたいなら散骨ですね
成仏できないんじゃないかという不安
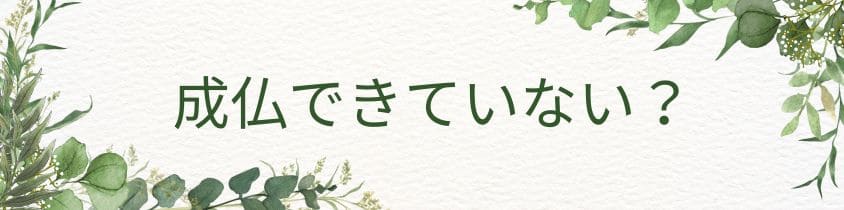
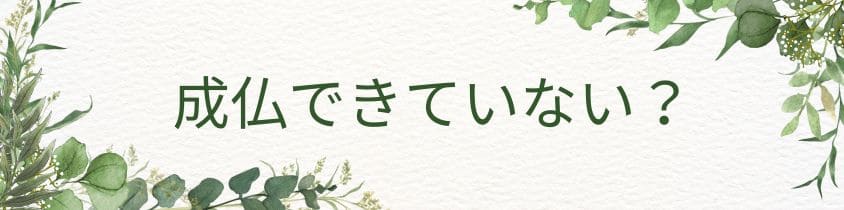
後から失敗したな~と思う悩みの一つが、「あれじゃ、成仏できないんじゃないか」という不安です。
一般的なお墓では、お坊さんにお経を上げてもらい、仏教による儀式が行われ、遺族はけじめや区切りをつけられます。
しかし、樹木葬は無宗教・無宗派なので、お願いしない限り供養はされません。お墓を建立したときに行われる開眼供養もありません。
そういった供養も、拒否される樹木葬もありますので、しっかりと調べる必要があります。
また、親族や家族の樹木葬への認知度の低さや、供養を行わないことから「成仏できない」と、後から文句を言われるケースもあります。
あらかじめしっかりと何度も説明して、全員に理解してもらってから、樹木葬をしたほうが良いですね。
参考:親族の同意が得られない?
別々の場所になった、一人用だった
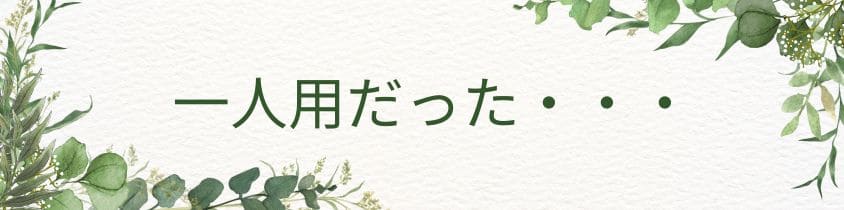
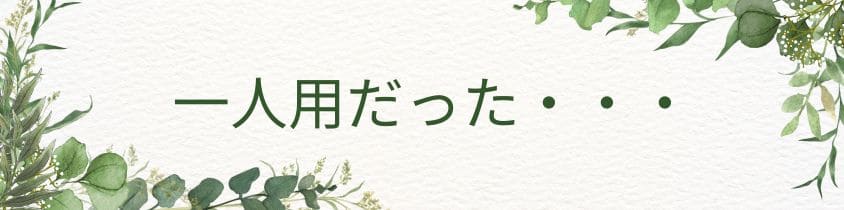
樹木葬のもう一つの失敗例として、家族や夫婦で一緒に眠ることができず、結果的に「別々の場所になってしまった」というケースがあります。
多くの樹木葬は、個別に埋葬するタイプが多く、一人用として設けられていることが多いです。
なので、家族で一つのお墓に入りたいと考えている方には、絶対に不向きです。
よく探せば夫婦用とか、4人まで、10人までといった樹木葬もありますが、基本的に本人用とか夫婦用になりますので、墓じまいには不向きな供養方法になります。
参考:先祖代々のお墓の墓じまい
考えていたよりも費用が高かった
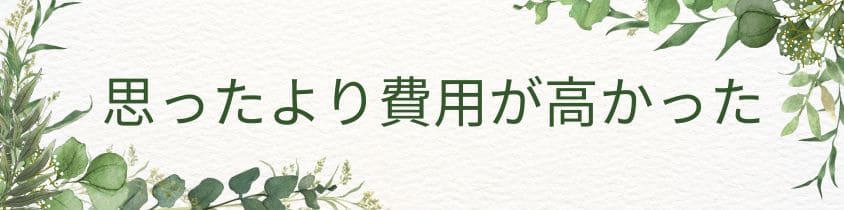
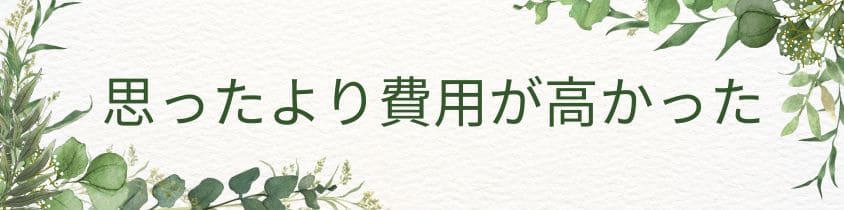
樹木葬は、一般的に「伝統的なお墓よりも安価で、手頃な供養方法」というイメージを持たれています。
しかし、実際には「想像以上に費用がかかった」と感じる人が多いです。
この理由としては、場所の選定や管理費用などが関わっているためです。
- アクセスが良い=高い
- 遺骨の数×金額
- 粉骨などの別途費用
アクセスが良い=高い
アクセスが良い都市部や景観が良い場所にある樹木葬の区画は、その利便性や魅力から価格が高く設定されています。
いわゆる都市型の樹木葬で、霊園の横にある場合が多いです。
当然ですが、東京都の23区内の地価と長野県の山奥の地価では、何百倍もの開きがありますよね。
それが反映されないわけがなく、そこへ行くための交通費や宿泊費などの雑費が毎回かかります。
なので、「樹木葬なのに、意外と高いよね~」と感じる方も多いです。



アクセスの良さを取るか、費用をとるか、考えるところです
遺骨の数×金額
ネットやチラシに書かれてる費用は一人分の埋葬だけでなく、遺骨1体(1柱)あたりの価格です。
家族の人数分とか、先祖代々の遺骨の分を確保しようとすると、費用がかなり増加します。
たとえば、1柱当たり5万円でも、4人で20万円、10人で50万円にもなってしまいます。
自分の分だけなら良いですが、何人分の樹木葬が必要なのか、まずはじめに考えてから探し始めるのが大切です。



多くのサイトに書かれてる金額は1人分です
粉骨の場合も
樹木葬によっては粉骨が必要だと言われるところもあります。
墓じまいの際には、粉骨だけじゃなくて洗骨や分骨も必要になる場合があります。
樹木葬を選ぶ際には、まずは樹木葬が安いというイメージを捨てましょう。
そのうえで、初期費用だけでなく、管理費や埋葬に関わる全体の費用を事前に把握しておくことが大切です。
参考:お金がない時の対処法
お墓参りが思っていたのと違った
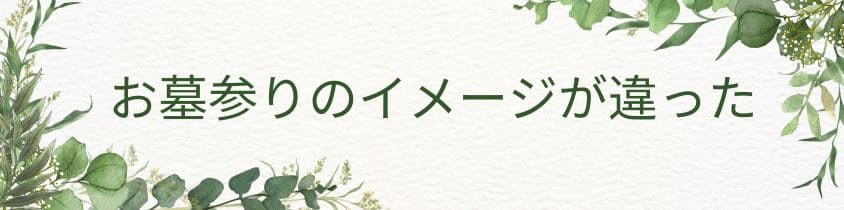
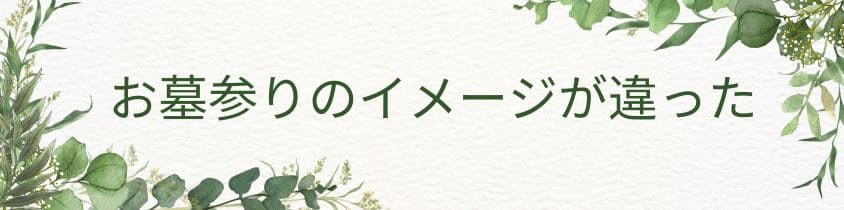
樹木葬において、お墓参りの方法が伝統的な墓石のお墓とは異なるため、期待していたのとは違うと感じる人が本当に多いです。
基本的に、個別型以外の樹木葬では、故人の名前が入ったプレートなどがなく、多くの遺骨が一か所にまとめて埋葬されているので、どこにいるのか全くわかりません。
そのため、「故人の正確な場所で手を合わせたい」と思っても、シンボルとなる樹木に手を合わせるしかできなくなります。
また、伝統的なお墓参りのようにお線香を焚いたり、献花をすることが制限されているところもあります。
特に、自然環境の保護を目的とした里山型の樹木葬などでは、花を供えることやお線香を焚くことが禁止されています。
こういったことがあると、あなたも「失敗した・・」と感じるかもしれませんし、家族や親族も「なんで樹木葬なんかにしたの?」と、あなたに文句をいってくるはずです。
でも、もう二度とやり直すのはできないので、諦めるしかなくなります。
そういったことがないよう、施設がどのようなお墓参りの方法を提供しているのか、制限事項は何かを事前に確認し、家族や親族にしっかりと説明して納得してもらうのが大切です。



一度現地に連れていくのが大事です
1墓に1本の樹木じゃなかった
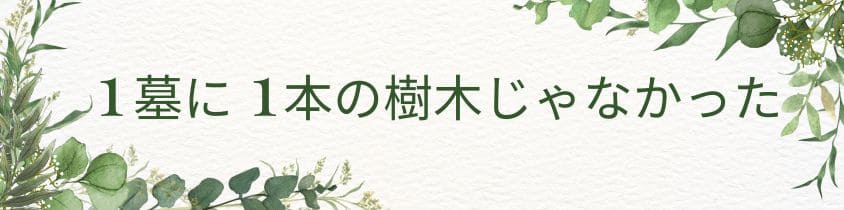
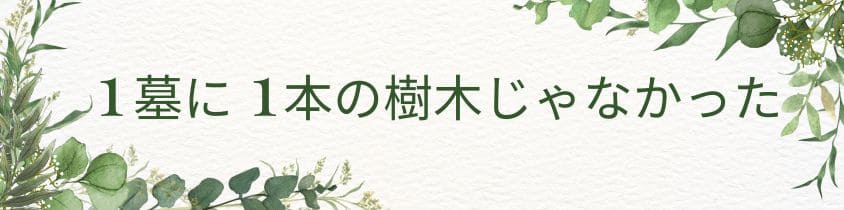
樹木葬に対して、一般的に「一本の木の下に眠る」というイメージを持っている方が多いですが、実際の現場では複数のお墓に1本の樹木が植えられている場合が多いです。
複数と言っても200個とか1000個くらいのお墓に1本の樹木だったり、樹木じゃなく草花や芝生になってるところもあります。
逆に、1つの遺骨に1本の樹木を植える樹木葬は、里山型と言われ、数えるほどしかありません。
樹木葬を運営している墓地管理者によって、植えられてる樹木も違いますし、植え方や見栄えも違うので、気に入るまで探されたほうが良いです。
樹木葬に多い樹木
- 桜
- ハナミズキ
- ヤマツツジ
- サルスベリ
- クスノキ
- カラマツ
- ポプラ
- エゾアジサイ
- もみじ
- ウメモドキ
- バラ
景観の変化で後悔
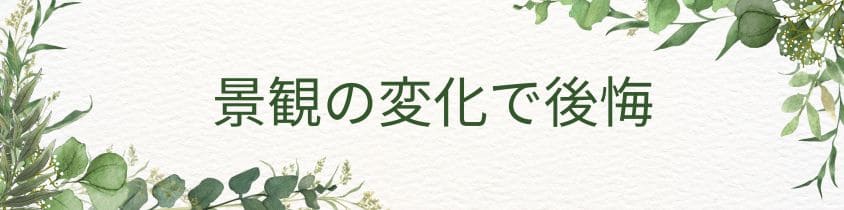
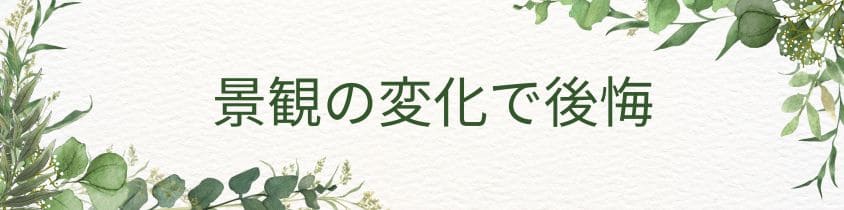
樹木葬は自然に囲まれているという特徴から、季節や天候によって景観が大きく変わります。
そのため、契約時には「美しい緑に囲まれた墓地」だったのが、違う季節に訪れるとその景観が大きく変わっていることにショックを受けることがあります。
例えば、冬の時期には草木が枯れ、樹木葬の墓地全体が寂しい雰囲気になることが少なくありません。
特に、里山タイプの樹木葬では、自然のままの景観を残すことを重視しているため、枯れた草や木の管理があまり行われないところもあり、季節ごとの変化が激しいです。
また、シンボルツリーが枯れてしまった場合、それを新しい木に植え替えるかどうかは施設の方針に依存します。
場合によっては追加費用が発生することもあり、これが想定外の出費や景観の悪化に繋がることもあります。
樹木葬を選ぶ際には、施設の管理方針について事前に確認するのと、季節を変えて何度も見に行ってみるのがとても大切になります。



季節によって、かなり違いますから気をつけて!
広告の見た目と現実の違い
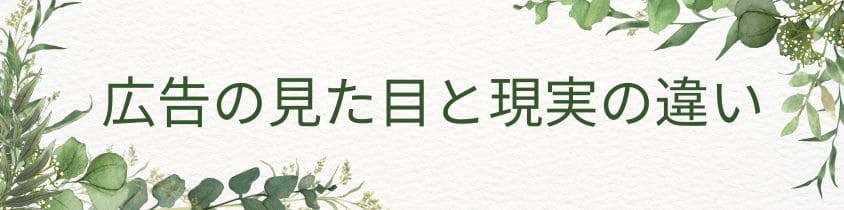
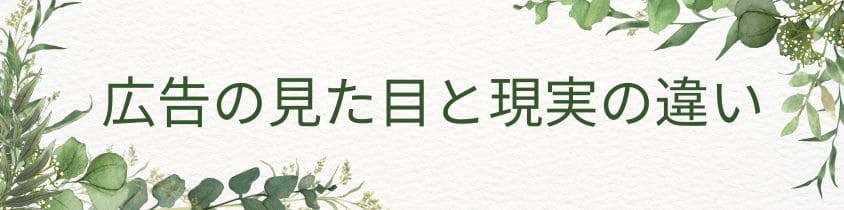
樹木葬の宣伝広告を見て、「自然豊かで美しい場所に眠りたい」と希望して契約する方も多いです。
しかし、実際に訪れてみると、広告の写真とは異なる現実に驚くことがあり、この点で失望する人も少なくありません。
広告には、霊園の美しい部分が強調されており、まるで理想的な自然の中で静かに眠れるように見せているからです。
このような後悔を避けるためには、契約前に必ず何度も現地を見学したり、複数の霊園を見比べて、広告だけで判断しないことが重要です。



広告は良い場所で、良い天気に、良い角度から写真を取ってます
管理不足で荒廃
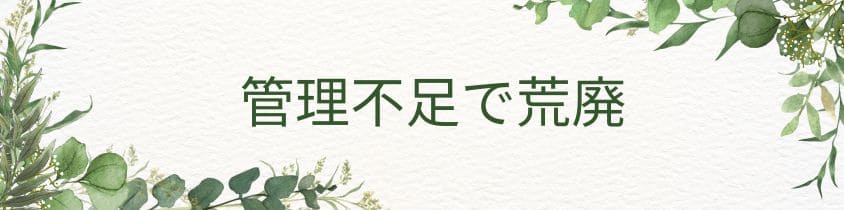
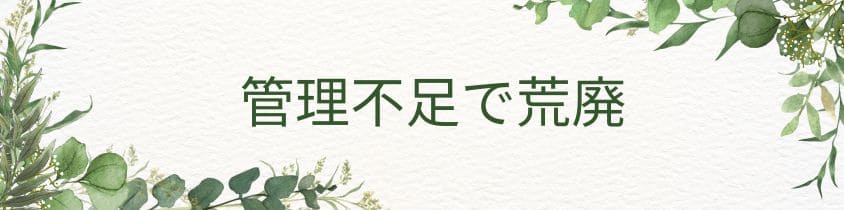
樹木葬している霊園の中には管理が行き届かず、霊園全体が荒れてしまうケースがあります。
例えば、霊園の手入れが不十分で雑草が生い茂っていたり、墓所にある木や草花が枯れて放置されていたり、シンボルツリーが枯れてしまったなんてこともあります。
このような管理不足の原因には、運営する母体の経営状況や樹木葬への取り組み方が悪い場合が往々にしてあります。
契約する前には、その施設の運営状況や経営母体についてしっかり確認し、事前の見学が絶対に必要です。



営業マンや管理人の人柄を見るのも大事です
アクセスが不便
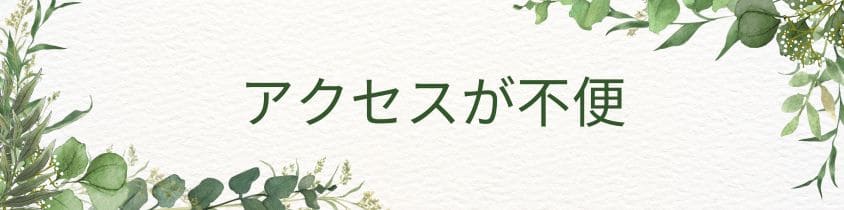
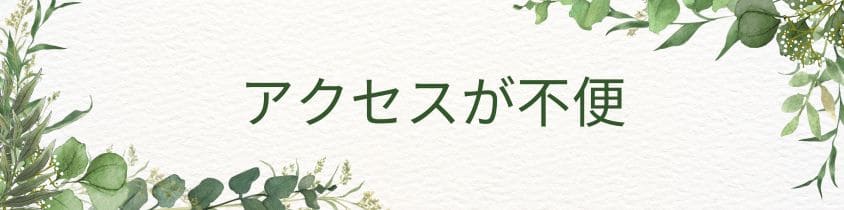
樹木葬の多くは、自然環境を重視して郊外や里山などに設置されていることが多く、アクセスが不便な場所にありがちです。
特に、高齢の家族がいる場合や、公共交通機関を利用して訪れることを考えている場合には、交通手段が限られている霊園は大きな負担となります。
また、今は大丈夫でも、10年後とか20年後になったときに、そこまで行けるのか、バリアフリーになっていて霊園の中を歩き回れるのかなどを、考えておく必要があります。
なので、樹木葬を選ぶ際には、現在だけでなく将来の訪問のしやすさも考慮することが重要です。



年令を重ねると難しくなることが増えます
虫の多さが問題
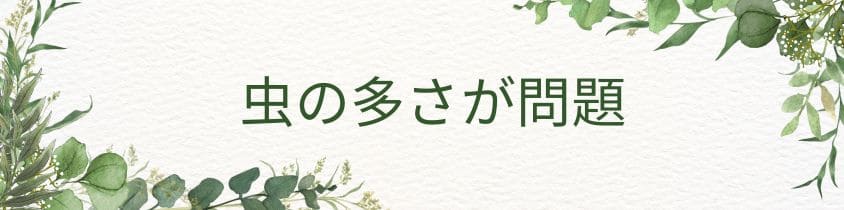
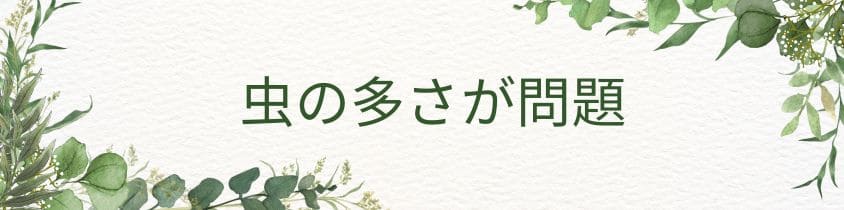
ある山あいにある樹木葬では、虫の多さに困ってしまったという失敗もよく聞かれます。
夏場や雨の多い時期には虫が大量に発生するのですが、自然を大事にするというコンセプトから、あまり積極的に対策をとらない霊園もあります。
また、管理する人が少ないので、蚊やハチなどの害虫はもちろん、雑草対策もままならないという所も多いです。
なので、季節ごとの虫の発生状況や施設の対策について事前に確認し、しっかりやってくれるところを選ぶのが大事です。



虫がでる時期に、実際に行ってみるのが大事です
家族や親族の反対
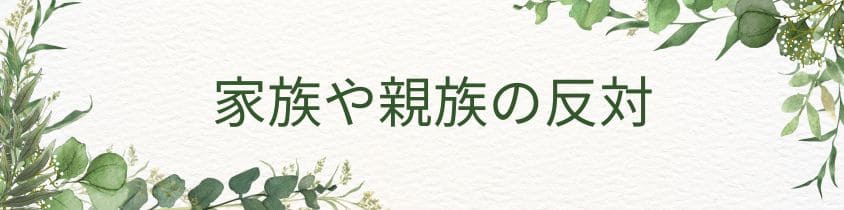
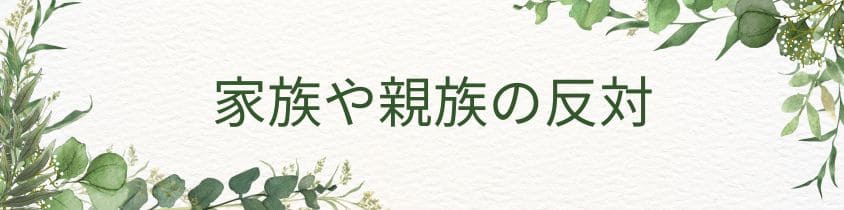
家族や親族にしっかり説明しておかないと、樹木葬は新しい供養の形式であるため、従来のお墓の形式を好む家族や親族から反対されることがあります。
「先祖代々の墓を守りたい」という気持ちを持つ人にとっては、従来の墓石のない樹木葬がなじみにくいと思うのがほとんどです。
これは、実際に墓石がなくなってから感じるケースがほとんどです。
「自然の中で眠りたい」「自然に還る」というと、幻想的でロマンチックな響きがあるので、なんとなく「良いな~」と思ってしまうのですが、いざその場所に行ってみて愕然とする方が、特に高齢者に多いです。
なので、たとえ良い返事をもらえたとしても、2~3回、その霊園に連れて行って、実際にどのようなお墓参りになるのかを体験させてあげるのが、とても大事になります。



失敗だと思う一番の原因は親族かもしれません
墓地管理の破綻
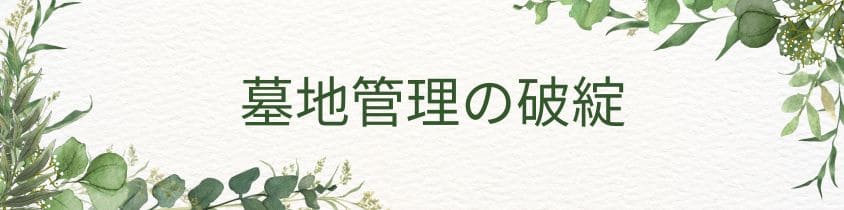
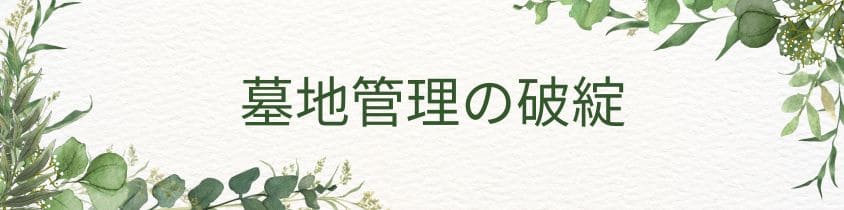
樹木葬を運営する霊園や寺院は、長期的な運営と維持が求められる施設ですが、財政状況が悪化し、墓地管理が破綻するケースもあります。
こればかりはどう仕様もできませんが、契約する前に、霊園だけでなく経営母体をしっかりと精査する必要があります。
引用元:東京商工リサーチ
見るべきポイントは、次の3つです。
- 運営年数や契約数
- 安すぎる永代供養料や管理費
- 相応しくない建物や過剰な広告
倒産したからと言ってすぐに何かをしなければいけないというのはありません。
引き受け手が現れれば再契約になりますし、どうしても引き受け手がいないときだけ、遺骨を引き取ることになります。



いきなり撤去されることはありません
ペット埋葬の制約
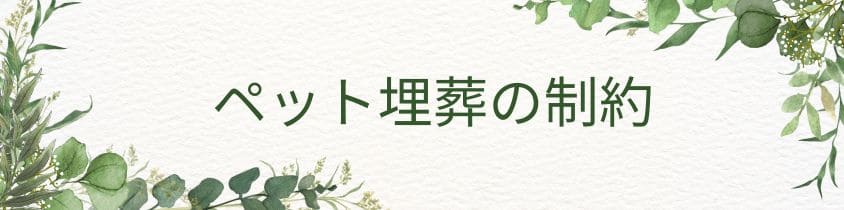
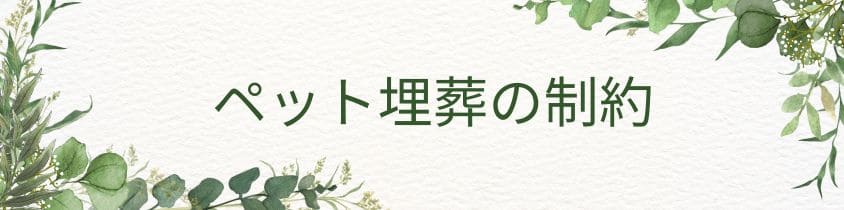
樹木葬には、ペットと一緒に埋葬できるタイプもありますが、全ての樹木葬がペットとの埋葬を許可しているわけではありません。
この点をしっかり確認しておかないと、後からペット不可がわかった場合、大きな後悔につながります。
ペットと一緒に埋葬できるかどうかは、霊園や墓地によって異なりますし。一般的にはペット可能の樹木葬は費用が高くなります。



ペットOKかどうかを第一優先で探されてみてください
合葬の抵抗感
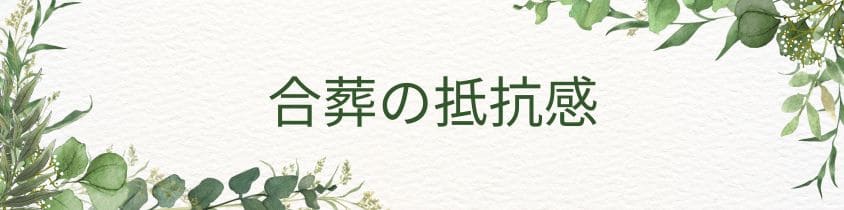
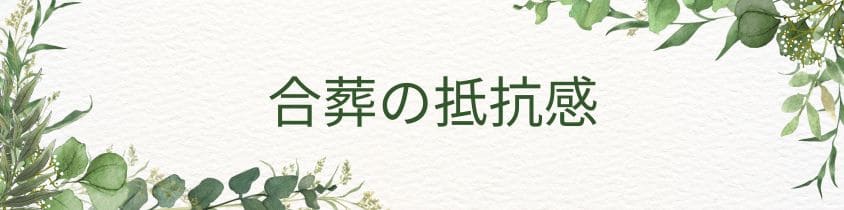
樹木葬には、合祀(ごうし)タイプの埋葬方法があります。合祀タイプとは、複数の人の遺骨を一つの墓所にまとめて埋葬する方法です。
ただ安いというだけで選んでしまうと、あとから抵抗を感じてしまう人が多いです。
「死んでまで他の人と一緒にいるのはちょっと」とか、「満員電車のようで嫌だ」といった声があります。
どのタイプの樹木葬にするか、家族や親族と徹底的に話し合うのが大切です。



合葬された本人は何も感じないので、供養する人の価値観です
契約期間の延長とその後の合葬


樹木葬には殆どの場合、契約期間が設定されていて、期間満了後には個別に埋葬されていた遺骨が合葬されます。
このことを理解せずに契約してしまい、後から「ずっと個別に管理してもらえると思っていた」と後悔したり、「契約延長してもらえなかった」と嘆いてるケースも多々あります。
契約期間は、霊園や樹木葬の種類によって異なり、13年から50年程度と幅がありますし、契約期間がなく霊園が続く限りずっと供養してもらえる所もあります。
このような事態を避けるためには、契約時に契約期間やその後の対応についてしっかり確認することが必要です。



この部分が一番大事です
樹木葬で失敗しないための下準備
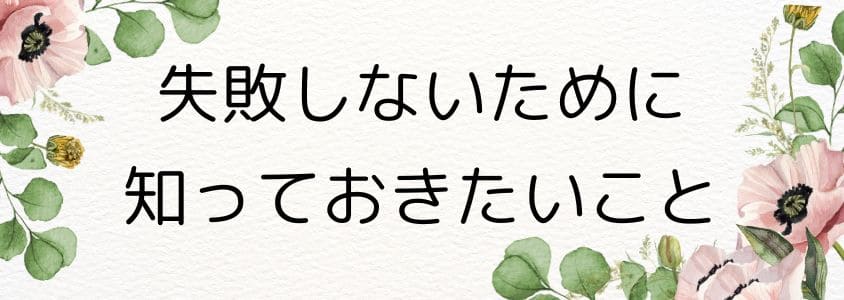
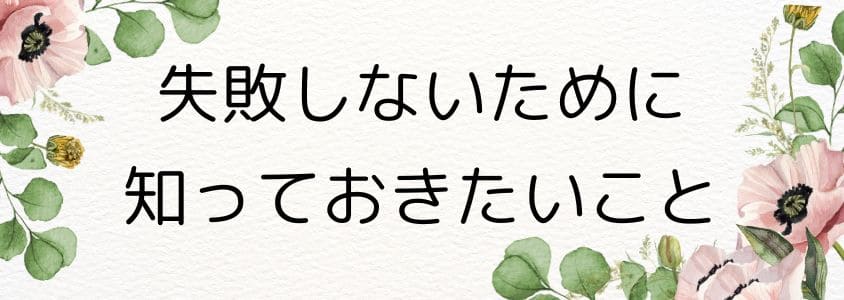
下準備にも知識を得る、計画をする、実行するの3段階あります。それぞれの方法を詳しく解説します。
- 樹木葬の実態と仕組み
- 費用はいくら?
- 永代供養できるのは1人
- 後悔しないための選び方ポイント
- 樹木葬をした芸能人
樹木葬の実態と仕組み
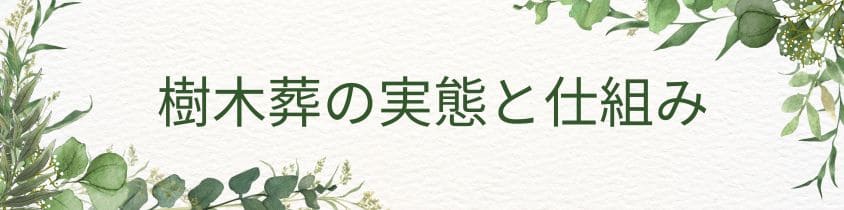
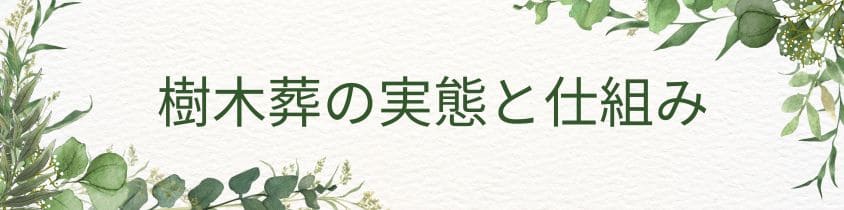
樹木葬とは、遺骨を墓石の代わりに樹木の下に埋葬する形のお墓で、自然と一体になりたいと考える方々に人気があります。
樹木葬にも里山型、公園型、ガーデン型の種類があり、それぞれに個別埋葬、合祀などの供養方法があります。
基本的には、樹木の下に埋葬されるので二度と取り出せなくなります。
つまり、合祀墓と同じですが、一つの大きな供養塔では味気ないので樹木にしているというイメージです。



墓石よりも華やかなイメージがありますね
費用はいくら?
樹木葬の費用は、場所やタイプ、供養方法によって違います。
- 里山型 50~80万円
- 公園型 5~80万円
- ガーデン型 10~100万円
- 個別型 50~100万円
- 集合型 20~50万円
- 合祀型 5~20万円
参考:樹木葬の実態
あくまでも目安ですが、基本的にアクセスや景観が良い個別型は高く、 合祀型は安いです。



安いと思っていたけど意外に・・・という方が多いです
永代供養できるのは1人
樹木葬は基本的に永代供養なのですが、実は、ほとんど1人用か夫婦用です。
つまり、両親と一緒の樹木葬に入るとか、先祖代々の墓を樹木葬に墓じまいするというのは、ほとんど無理です。
たとえ同じ樹木葬の場所に埋葬したとしても、別々な場所に埋葬されることになります。
なので、基本的に樹木葬はまだお墓を持っていない方で、跡継ぎがいなかったり、お墓を作って残したくない方向けのものです。



墓じまいには向いてません
後悔しないための選び方の下準備
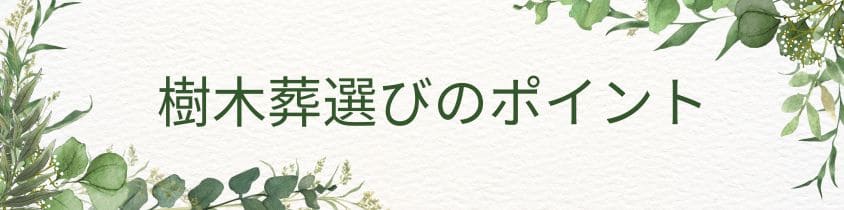
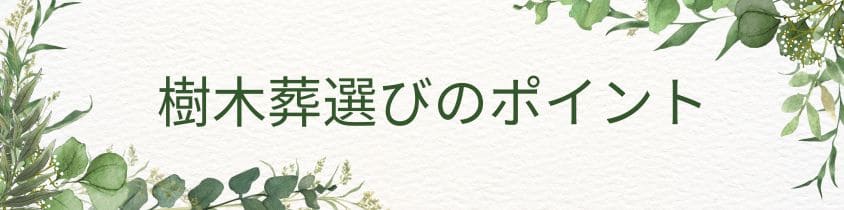
後悔しないための樹木葬選びの下準備は、5つです。
- 実際の場所を何度も見学
- 運営母体の経営状況を確認
- 契約内容の確認
- 人数の確認
- 家族や親族の説得
実際の場所を何度も見学
上述した失敗例でもよくありましたが、思っていたイメージと実際に行ってみた景観が違うと、一番後悔します。
管理がされてなかったり、冬が寂しすぎたり、虫がたくさん出たり、はじめに見た景色と違う・・などです。
そんな失敗をしないためにできることはたった一つです。時間を変え、季節を変え、別な天候の時に何度も出向いて確かめることです。
できれば、親族や家族と一緒に出かけたり、一人で行っても写真を残して、皆で相談するのがとても大切です。
運営母体の経営状況を確認
運営母体の経営状態はもちろん、管理人の人柄や営業担当の人柄もとても重要なファクターです。
というのも、一度決めたら二度と変えられないからです。
運営母体が倒産してしまったら、同仕様もないです。再びお金をはらう事になりかねません。
見た目だけじゃなくて裏側も,ネットの情報や口コミなどを使ってしっかりと確認しましょう。
契約内容の確認
年を取ってくると小さな字は見えづらいものです。
だからといって、大切なことが書かれてる契約書をしっかりと読まないで契約してしまうと、思わぬ落とし穴にハマってしまう事になります。
たとえば、10年後には合祀されるとか、管理費以外にも支払うお金が必要だったり、やってはいけないことなどがしっかりと書かれてるはずです。
なので、たとえ読みづらくてもしっかりと契約書を読んで、所有者の権利などについて確かめておくのが必要です。
人数の確認
樹木葬は樹木が植えられてる下の地面に、穴をほって遺骨を埋めるものですが、人数制限があります。
1人用だったり、夫婦用だったり、4人までとか、はじめに説明があるはずです。
それを確かめずに契約してしまうと、隣同士になれると思っていたはずが、夫婦といっても10m先に埋葬されてしまうケースもよくあります。
また、はじめは夫婦揃って埋葬されても、10年後には他の人と一緒に合祀される契約も多いですので、人数の確認といつまでその場所に埋葬されるのかをしっかりと確かめましょう。
家族や親族の説得
公開しないためにいちばん大切なのが、家族や親族を説得して、樹木葬に納得してもらうことです。
樹木葬した後に色々と文句を言われ続けると、誰しも心が折れて後悔し始めます。
逆に感謝されれば、たとえ少しくらい後悔していても良かったと思い直すものです。
いずれにせよ、一度しかできないことで、二度とやり直すのはできないので、しっかりと関係する皆さんに納得してもらうのがとても大切になります。



実際に樹木葬をしてもらうには、代行業者がおすすめです
おすすめの代行業者3選
墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。
「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から


「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。
サービス内容はこちら。
- お墓の撤去
- 離檀代行・サポート
- 行政手続きサポート
- 撤去業者持ち込み交渉
- 墓じまい全体のサポート
離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。
サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。
安心・安全の「イオンの墓じまい」


日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。
基本的なサービスがワンセットになっています。
- 行政手続き
- お骨の取り出し
- 墓石の解体・処分
- 墓地を更地に戻す
- お骨の受け渡し
公式サイトから詳細の金額をご確認ください。
\ 無料相談はこちら /



イオンカードも使えます
すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」


面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。
サービス内容はこちら。
- 行政手続き代行
- ご遺骨の取り出し
- 墓石の解体・処分
- 墓所の変換
行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。
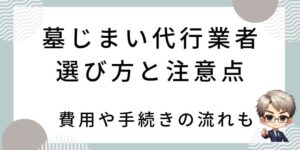
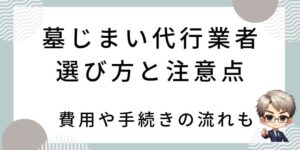
樹木葬をした芸能人
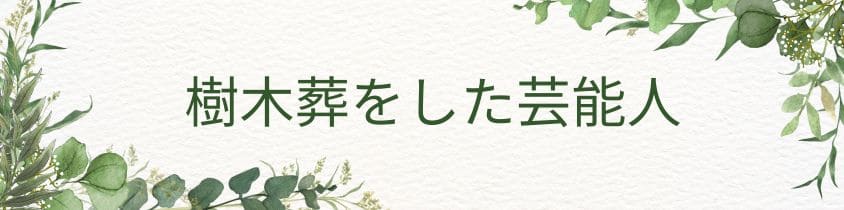
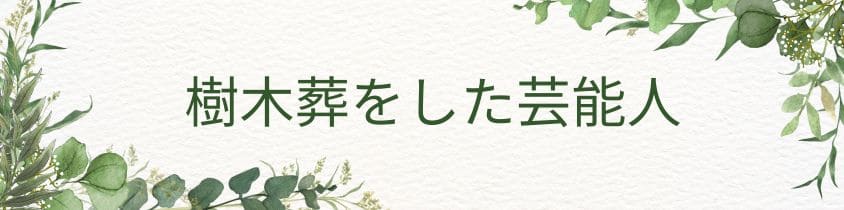
樹木葬をされてる芸能人はこちらです。
- 立花隆氏(ジャーナリスト・評論家)
- 市原悦子さん(俳優)
海洋散骨された方は石原裕次郎氏や勝新太郎氏、横山やすし氏など多数いますが、樹木葬はまだまだ少ないです。
ただ、お墓はいらないと言ってる方も多くいらっしゃるので、これから徐々に増えていくのではないでしょうか。
樹木葬でよくある質問
- 樹木葬でよくある失敗例は?
-
樹木葬でよくある失敗例には以下のようなものがあります
- 「自然に還る」と思っていたが、実際にはコンクリート納骨で土に還らない
- 契約期間終了後に合葬されることを知らなかった
- 家族や親族が反対し、供養の形式を巡ってトラブルに発展
- 広告のイメージと現実が大きく異なり、期待外れだった
- 景観の変化や虫の多さが想定外だった
- 費用が予想以上に高額だった
- 樹木葬を選ぶ際に確認すべきポイントは?
-
以下のポイントを事前に確認することが重要です
- 実際の場所を何度も訪れて、景観やアクセスの確認
- 運営母体の経営状況や霊園の管理体制
- 契約期間や合葬の有無、人数制限などの契約内容
- 家族や親族との意見交換と納得
- 「自然に還る」とはどういう意味?
-
樹木葬の「自然に還る」という表現は、遺骨が自然の中に埋葬されることを指しますが、実際には次のような意味があります。
- 火葬された遺骨はセラミック状になっており、分解には数百年かかる
- コンクリート納骨の場合は土に還ることはない
- 遺骨をパウダー状にして埋葬することで、自然に還りやすくなる場合もある
- 樹木葬の費用が高くなる理由は?
-
樹木葬の費用が予想以上に高くなる理由は以下の通りです。
- 都市部やアクセスが良い場所では地価が高いため
- 遺骨の数に応じた費用が必要
- 粉骨や分骨などの追加処理費用
事前に総費用を確認することでトラブルを回避できます。
- 親族や家族の説得が重要なのはなぜ?
-
樹木葬は従来のお墓とは異なる供養方法のため、親族や家族の理解が欠かせません。
説得不足が原因で次のような結果になりがちです。
- 供養方法への不満が後にトラブルに発展する
- 「成仏できないのでは?」という不安が残る
- お墓参りの形式が期待と違い、失望される
家族全員の納得を得ることが、後悔しない選択のカギです。
まとめ:樹木葬で失敗しないための方法
この記事のまとめです。
- 樹木葬には多くの失敗例があり、事前のリサーチが重要
- 遺骨はコンクリート穴に納骨されていることが多い
- なので自然には還らない
- 火葬されると、遺骨の表面がセラミックになる
- なので遺骨が自然に還るには数百年掛かる
- 契約内容や費用が予想以上であるケースが多い
- 樹木葬の景観は季節や天候で大きく変わるため後悔しやすい
- 供養の形式が従来の墓と異なり、親族が反対することがある
- アクセスの悪さが原因でお墓参りが不便になることも
- 管理不足で樹木や草花が荒廃し、見た目が悪くなる場合も
- 家族や夫婦で一緒に埋葬できず、別々になることも多い
- 複数の遺骨が1本の樹木の下に埋葬される
- 樹木葬にはペットの埋葬が制限される場合がある
- 合葬形式に抵抗を感じる人が多い
- 契約期間終了後に合祀され、永遠には供養されない
- 「自然に還る」というキャッチフレーズと実態が異なる
- 家族や親族の説得が不十分で後悔するケースがある



最後まで読んでいただきありがとうございました!
厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要